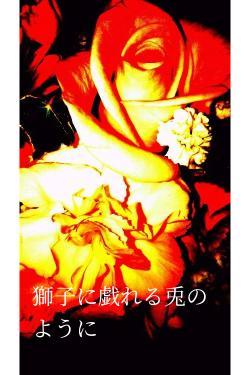信長はスクッと立ち上がり、紅は視線を落としたまま、信長の後ろに続いた。
もうこれで、紅と逢うこともないのかもしれない。
寂しさに押し潰されそうになりながらも、私はその後ろ姿を見送るしかなかった。
―4月、長良川の戦い―
信長は斎藤道三救援のために、紅と共に木曽川を越え美濃の大浦まで出陣。紅にとってこれが初陣となった。
“しかし到着した時には、斎藤道三は子息である斎藤義龍にすでに敗れ戦死を遂げていた。”
清州城にいた私にも、その訃報は届いた。蝮と恐れらた斎藤道三が、我が子に死に追いやられるとは……。
偽りの間柄とはいえ、父である斎藤道三を失い、戦国の世の無情に涙した。
紅も私の側から退き、信長と共に合戦に同行している。2人が常に命の危険に曝されていることを改めて痛感する。
不安な私の心を慰め、心の隙間を埋めてくれたのは、帰蝶の従兄弟である明智光秀からの文だった。
光秀からの文は、信長に輿入れした翌月より年に数通届いた。その内容は、常に私の体調を案じ、文面の最後には【何かあらばすぐに馳せ参ずる】と書かれていた。離れていても、その言葉が何よりも心強かった。
(光秀殿……)
「於濃の方様、土田御前様のお成りでございます」
襖越しに声を掛けられ、光秀からの文を急いで片付ける。
(土田御前様……)
土田御前は信長の生母。
信長と反りが合わず、弟信勝を溺愛していた。
土田御前の待つ座敷に出向き、私は深々と頭を下げる。
「そなたの父上であらせられる斎藤道三殿ご逝去に際し、お悔やみを申し上げまする」
土田御前は私を真っ直ぐ見つめ、さらに言葉を続けた。
「このような時に酷ではあるが、そなたはいまだに子が授からぬ。侍女に聞くところによると、信長ともう何年も夜伽をしておらぬそうじゃな」
(……申し訳ござりませぬ)
「正室が子を成さねば家督争いの火種となりましょう。それはお分かりですね」
(……はい)
「この度、信長が見初めた女子を正式に側室とすることと相成った。名は生駒吉乃と申す。吉乃が男子を産めば、織田家の世継ぎとなる。それが意にそぐわねば、信長を引き止め夜伽に励むがよい」
土田御前はそう言い放つと、侍女と共に座敷をあとにする。
信長に側室……。
戦国の世に複数の側室を持つことは珍しいことではないが、信長が見初めた女性であるならば、体だけではなく心まで奪われたも同然。
土田御前は斎藤道三が亡くなり、子も生めない人質は、もう価値はないと仰られたに過ぎない。
子が出来ないなら信長と離縁しろと、遠回しに宣告されたのだ。
もうこれで、紅と逢うこともないのかもしれない。
寂しさに押し潰されそうになりながらも、私はその後ろ姿を見送るしかなかった。
―4月、長良川の戦い―
信長は斎藤道三救援のために、紅と共に木曽川を越え美濃の大浦まで出陣。紅にとってこれが初陣となった。
“しかし到着した時には、斎藤道三は子息である斎藤義龍にすでに敗れ戦死を遂げていた。”
清州城にいた私にも、その訃報は届いた。蝮と恐れらた斎藤道三が、我が子に死に追いやられるとは……。
偽りの間柄とはいえ、父である斎藤道三を失い、戦国の世の無情に涙した。
紅も私の側から退き、信長と共に合戦に同行している。2人が常に命の危険に曝されていることを改めて痛感する。
不安な私の心を慰め、心の隙間を埋めてくれたのは、帰蝶の従兄弟である明智光秀からの文だった。
光秀からの文は、信長に輿入れした翌月より年に数通届いた。その内容は、常に私の体調を案じ、文面の最後には【何かあらばすぐに馳せ参ずる】と書かれていた。離れていても、その言葉が何よりも心強かった。
(光秀殿……)
「於濃の方様、土田御前様のお成りでございます」
襖越しに声を掛けられ、光秀からの文を急いで片付ける。
(土田御前様……)
土田御前は信長の生母。
信長と反りが合わず、弟信勝を溺愛していた。
土田御前の待つ座敷に出向き、私は深々と頭を下げる。
「そなたの父上であらせられる斎藤道三殿ご逝去に際し、お悔やみを申し上げまする」
土田御前は私を真っ直ぐ見つめ、さらに言葉を続けた。
「このような時に酷ではあるが、そなたはいまだに子が授からぬ。侍女に聞くところによると、信長ともう何年も夜伽をしておらぬそうじゃな」
(……申し訳ござりませぬ)
「正室が子を成さねば家督争いの火種となりましょう。それはお分かりですね」
(……はい)
「この度、信長が見初めた女子を正式に側室とすることと相成った。名は生駒吉乃と申す。吉乃が男子を産めば、織田家の世継ぎとなる。それが意にそぐわねば、信長を引き止め夜伽に励むがよい」
土田御前はそう言い放つと、侍女と共に座敷をあとにする。
信長に側室……。
戦国の世に複数の側室を持つことは珍しいことではないが、信長が見初めた女性であるならば、体だけではなく心まで奪われたも同然。
土田御前は斎藤道三が亡くなり、子も生めない人質は、もう価値はないと仰られたに過ぎない。
子が出来ないなら信長と離縁しろと、遠回しに宣告されたのだ。