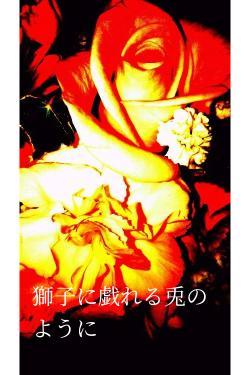「安心しろ。帰蝶とは契りを交わしてはおらぬ。わしは紅を好いておるのじゃ」
信長はあたしの体を優しく愛撫する。
8年もの間、晒しできつく押さえつけれていた乳房が、信長の手で解き放たれ女に戻る。
「……ああ」
抵抗するものの、耳元で『紅を好いておるのじゃ』と囁かれ、体から力が抜け落ち、自然と声が漏れた。
越えてはならない男と女の一線。
頭では理解できているのに、体に力が入らない。
信長はあたしの変化を察知し、掴んでいた手を離し、袴の帯をするするとほどいた。
「……だめ」
信長はあたしの指に、自分の指を絡めた。
ずっと抑えていた熱い感情が……。
一気に溢れ出す。
あたしがお慕いする人は……。
暴君で手がつけられない大うつけだ……。
「紅、わしの側に仕えよ」
「……なりませぬ」
「わしのものになれ」
イヤイヤと首を振るものの、絡めた指はわたしの心を離してはくれない。
「暴れるでない。己の心に従え」
「……のぶなが……さま」
信長は狡い男だ。
帰蝶という正室がありながら、女にうつつを抜かす。
1人の女を愛することも出来ないくせに、男と偽るあたしを面白半分に抱いているに違いない。
それなのに、あたしは……。
あたしは……。
そんな信長を……。
信長はあたしの体を優しく愛撫する。
8年もの間、晒しできつく押さえつけれていた乳房が、信長の手で解き放たれ女に戻る。
「……ああ」
抵抗するものの、耳元で『紅を好いておるのじゃ』と囁かれ、体から力が抜け落ち、自然と声が漏れた。
越えてはならない男と女の一線。
頭では理解できているのに、体に力が入らない。
信長はあたしの変化を察知し、掴んでいた手を離し、袴の帯をするするとほどいた。
「……だめ」
信長はあたしの指に、自分の指を絡めた。
ずっと抑えていた熱い感情が……。
一気に溢れ出す。
あたしがお慕いする人は……。
暴君で手がつけられない大うつけだ……。
「紅、わしの側に仕えよ」
「……なりませぬ」
「わしのものになれ」
イヤイヤと首を振るものの、絡めた指はわたしの心を離してはくれない。
「暴れるでない。己の心に従え」
「……のぶなが……さま」
信長は狡い男だ。
帰蝶という正室がありながら、女にうつつを抜かす。
1人の女を愛することも出来ないくせに、男と偽るあたしを面白半分に抱いているに違いない。
それなのに、あたしは……。
あたしは……。
そんな信長を……。