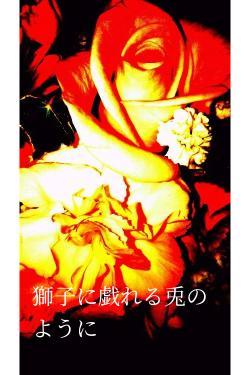「……企むなど、断じてありませぬ」
「薄々感付いてはいたが、まさか本当に女だったとは……」
薄々感付いていた!?
「わざと……俺を木刀で打ちのめしたのか!」
信長は不敵な笑みを浮かべる。
「紅と同じ床でやすんだときに、男とは異なる匂いを感じ妙な気持ちを抱いた。このわしが男にそのような気持ちを抱くとは、どうしても腑に落ちなかった。そのモヤモヤした気持ちが何なのか、この目で確かめたかった」
信長はあたしを組み伏せ、体を拘束した。
「大声を出すでない。帰蝶や侍女に気付かれてもよいのか?」
「……っ、信長様、どうか……お許しを」
「やっとわしの名を呼んだな。紅がそのようなしおらしい声を出すとはのう。男を抱いているようで、奇妙じゃ」
信長の唇がゆっくりと落ちてきた。あたしの唇を啄むようにキスをする。
「……っ、は、離せ」
抵抗しているあたしの両手を、左手で掴み頭上で束ねる。信長の舌はあたしの口内を弄び、右手はあたしの首筋をなぞる。
「美しき肌……。なぜ、もっと早く気付けなかったのか」
耳の後ろに滑り込んだ手は、あたしに逃げ場を与えないようにガッチリと後頭部を押さえ、激しいキスの雨を降らせた。
バタバタと足をばたつかせたが、信長の体と筋肉質な太股が、その動きを封じ込める。
「……お願い。やめて……。於濃の方様を裏切りたくないの」
「薄々感付いてはいたが、まさか本当に女だったとは……」
薄々感付いていた!?
「わざと……俺を木刀で打ちのめしたのか!」
信長は不敵な笑みを浮かべる。
「紅と同じ床でやすんだときに、男とは異なる匂いを感じ妙な気持ちを抱いた。このわしが男にそのような気持ちを抱くとは、どうしても腑に落ちなかった。そのモヤモヤした気持ちが何なのか、この目で確かめたかった」
信長はあたしを組み伏せ、体を拘束した。
「大声を出すでない。帰蝶や侍女に気付かれてもよいのか?」
「……っ、信長様、どうか……お許しを」
「やっとわしの名を呼んだな。紅がそのようなしおらしい声を出すとはのう。男を抱いているようで、奇妙じゃ」
信長の唇がゆっくりと落ちてきた。あたしの唇を啄むようにキスをする。
「……っ、は、離せ」
抵抗しているあたしの両手を、左手で掴み頭上で束ねる。信長の舌はあたしの口内を弄び、右手はあたしの首筋をなぞる。
「美しき肌……。なぜ、もっと早く気付けなかったのか」
耳の後ろに滑り込んだ手は、あたしに逃げ場を与えないようにガッチリと後頭部を押さえ、激しいキスの雨を降らせた。
バタバタと足をばたつかせたが、信長の体と筋肉質な太股が、その動きを封じ込める。
「……お願い。やめて……。於濃の方様を裏切りたくないの」