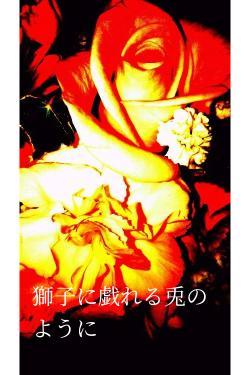その夜、信長は寝所に戻ることはなく、私は一睡もできないまま朝を迎えた。
信長を怒らせてしまった。
抵抗しないで、抱かれてしまえば良かったのに。
後悔しても、もう遅い。
「御殿様、帰蝶様、お目覚めでございますか? 殿と小見の方様が御立ちでございます。新しき着物を持参致しましたゆえ、お召しかえを……」
多恵が寝所に入り、信長の姿がないことに驚いている。
「帰蝶様、御殿様はいずこへ?」
信長と夜を共にしていないことが知れたら、斎藤道三や小見の方に申し訳がたたない。
私は俯いたまま多恵が持参した着物に袖を通す。真新しい姫衣は、藤紫で金糸の鶴が舞う鮮やかなもの。
「この打ち掛けは、御殿様が帰蝶様の為にご用意されたそうですよ」
私のために……
あの信長が……?
「祝言ではあのような無礼な態度ではござりましたが、ああ見えて優しいお方なのやも知れませぬなあ。ほんに美しい着物でございますこと。帰蝶様にようお似合いでございます」
昨夜の乱暴な振る舞いと、突き放したような暴言。信長をそうさせたのは、この私……。
私は美濃国に戻る斎藤道三と小見の方の一行を見送るために正門を出る。この城に残るのは、多恵と数名の侍女だけ。
「帰蝶、信長殿と仲むつまじく、元気な若子様を生むのじゃ。それがそなたの務めなり。よいな」
(はい)
私は道三の言葉に頭を垂れる。
光秀は別れ際に私を見つめ、優しい言葉を掛けてくれた。
「帰蝶、何か困ったことあらば文をよこすがよい。すぐに馳せ参ずる」
(はい)
一行は出立し、私は不安に苛まれる。
正室としての役目を果たせないなら、離縁どころか斎藤家との和睦も暗礁に乗り上げたも同然。
すべては……。
この私にかかっている。
信長を怒らせてしまった。
抵抗しないで、抱かれてしまえば良かったのに。
後悔しても、もう遅い。
「御殿様、帰蝶様、お目覚めでございますか? 殿と小見の方様が御立ちでございます。新しき着物を持参致しましたゆえ、お召しかえを……」
多恵が寝所に入り、信長の姿がないことに驚いている。
「帰蝶様、御殿様はいずこへ?」
信長と夜を共にしていないことが知れたら、斎藤道三や小見の方に申し訳がたたない。
私は俯いたまま多恵が持参した着物に袖を通す。真新しい姫衣は、藤紫で金糸の鶴が舞う鮮やかなもの。
「この打ち掛けは、御殿様が帰蝶様の為にご用意されたそうですよ」
私のために……
あの信長が……?
「祝言ではあのような無礼な態度ではござりましたが、ああ見えて優しいお方なのやも知れませぬなあ。ほんに美しい着物でございますこと。帰蝶様にようお似合いでございます」
昨夜の乱暴な振る舞いと、突き放したような暴言。信長をそうさせたのは、この私……。
私は美濃国に戻る斎藤道三と小見の方の一行を見送るために正門を出る。この城に残るのは、多恵と数名の侍女だけ。
「帰蝶、信長殿と仲むつまじく、元気な若子様を生むのじゃ。それがそなたの務めなり。よいな」
(はい)
私は道三の言葉に頭を垂れる。
光秀は別れ際に私を見つめ、優しい言葉を掛けてくれた。
「帰蝶、何か困ったことあらば文をよこすがよい。すぐに馳せ参ずる」
(はい)
一行は出立し、私は不安に苛まれる。
正室としての役目を果たせないなら、離縁どころか斎藤家との和睦も暗礁に乗り上げたも同然。
すべては……。
この私にかかっている。