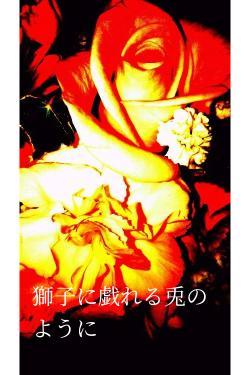「だって……美濃。こうでもしないと……収まりがつかないから……」
「紗紅、いい加減目をさましなさい!」
美濃が私の頬を叩いた。
私を叩いたくせに、美濃の目には涙が滲んでいる。
叩かれた頬はジンジンと痛む。
それなのに、心はその何倍も痛んだ。
あたしは厄介者なんだ。
母も姉も世間体を気にし、あたしを追い出そうとしている。
強風に煽られくるくると回転する凧のように、張り詰めていた糸がプツンと切れた。
「うっせぇ! こんな家、出て行ってやる! もう二度と帰らねぇかんな!」
あたしは椅子の背凭れに掛けていた黒いジャンパーを引ったくるように取り、アパートを飛び出した。
川沿いに立ち並ぶ公営住宅。コンクリートの階段を駆け下りると、アパートの前に面した公道で、彼がバイクに跨がりあたしを待っていた。
織田信也、20歳。
先週渋谷でナンパされ、あたしと信也は知り合った。あたし達はすぐに意気投合し付き合い始めた。
「紗紅、おせーぞ」
信也は黒いフルフェースのヘルメットをあたしに差し出す。
信也は元暴走族だ。
龍刃連合と言えば、この界隈で知らない者はいない。
18歳で族を引退し、今は小さな整備工場で働いている。
信也に渡されたヘルメットを被り、広い背中に抱き着く。ひんやりとした革ジャンが、怒りで逆流していたあたしの血を鎮める。
「飛ばすぞ。しっかり掴まってろよ」
「むしゃくしゃするから、ぶっ飛ばして」
バイクは爆音を鳴らし、夜の公道を走り抜ける。真冬の風は肌を刺すように冷たく、凍える体を信也の背中に密着させ、温もりを求めた。
信也は暴走族がよくたむろする馴染みの居酒屋へ、あたしを連れて行った。
「紗紅、いい加減目をさましなさい!」
美濃が私の頬を叩いた。
私を叩いたくせに、美濃の目には涙が滲んでいる。
叩かれた頬はジンジンと痛む。
それなのに、心はその何倍も痛んだ。
あたしは厄介者なんだ。
母も姉も世間体を気にし、あたしを追い出そうとしている。
強風に煽られくるくると回転する凧のように、張り詰めていた糸がプツンと切れた。
「うっせぇ! こんな家、出て行ってやる! もう二度と帰らねぇかんな!」
あたしは椅子の背凭れに掛けていた黒いジャンパーを引ったくるように取り、アパートを飛び出した。
川沿いに立ち並ぶ公営住宅。コンクリートの階段を駆け下りると、アパートの前に面した公道で、彼がバイクに跨がりあたしを待っていた。
織田信也、20歳。
先週渋谷でナンパされ、あたしと信也は知り合った。あたし達はすぐに意気投合し付き合い始めた。
「紗紅、おせーぞ」
信也は黒いフルフェースのヘルメットをあたしに差し出す。
信也は元暴走族だ。
龍刃連合と言えば、この界隈で知らない者はいない。
18歳で族を引退し、今は小さな整備工場で働いている。
信也に渡されたヘルメットを被り、広い背中に抱き着く。ひんやりとした革ジャンが、怒りで逆流していたあたしの血を鎮める。
「飛ばすぞ。しっかり掴まってろよ」
「むしゃくしゃするから、ぶっ飛ばして」
バイクは爆音を鳴らし、夜の公道を走り抜ける。真冬の風は肌を刺すように冷たく、凍える体を信也の背中に密着させ、温もりを求めた。
信也は暴走族がよくたむろする馴染みの居酒屋へ、あたしを連れて行った。