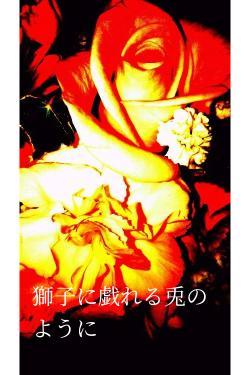信長とあたしの一騎打ち。
しんしんと降る雪の中で、木刀は激しい音を鳴らす。これが真剣なら、あたしは斬り殺されているだろう。
信長に叩きのめされ、足の痛みに耐えきれず、あたしは地面に倒れた。信長は勝ち誇ったように、あたしに木刀を突きつけ見下ろした。
「傷を負いながら互角に打ち合うとは、なかなかの腕前。平手、怪我の手当てをしてやれ」
「手当てとな。信長様、この男をどうなさるおつもりで?」
「たいそう興味深い男ゆえ、わしの側に仕えさせる。平手が、この者を指南せよ」
「な、なんと。信長様一人でも手を焼いておるというのに、このような無法者までわしに指南しろと」
「平手、何か申したか?」
「いえ、何でもござりませぬ」
平手は苦虫を噛みつぶしたような顔で、あたしを見た。信長は木刀であたしの顎を持ち上げた。
「貴様の名を聞いてなかったな。名は何と申す」
「……紅」
「紅とな? 変わった名だな。その形は目にあまる。そなたに羽織袴を授けよう。怪我の手当てを受け着替えるがよい」
信長はあたしに背を向け、汚れた足をたらいで洗いその場から立ち去る。
あたしは家臣に支えられ縁側に座り、足を洗い奥座敷に通された。平手は家臣に「もう下がってよい」と告げる。
あたしは痛む足を庇いながら、畳の上に座る。平手はあたしの前にドッカリと腰を降ろした。
「このような変わった身形をした男は初めてじゃ」
平手はあたしのズボンを膝まで捲り上げ、傷の手当てをした。
「男のくせにすね毛もなく、色白でスベスベとした肌じゃのう。筋肉もなく細くて折れそうじゃ。満足に食してないのか」
平手は焼酎を口に含み、傷口にブーッと吹きかけた。
しんしんと降る雪の中で、木刀は激しい音を鳴らす。これが真剣なら、あたしは斬り殺されているだろう。
信長に叩きのめされ、足の痛みに耐えきれず、あたしは地面に倒れた。信長は勝ち誇ったように、あたしに木刀を突きつけ見下ろした。
「傷を負いながら互角に打ち合うとは、なかなかの腕前。平手、怪我の手当てをしてやれ」
「手当てとな。信長様、この男をどうなさるおつもりで?」
「たいそう興味深い男ゆえ、わしの側に仕えさせる。平手が、この者を指南せよ」
「な、なんと。信長様一人でも手を焼いておるというのに、このような無法者までわしに指南しろと」
「平手、何か申したか?」
「いえ、何でもござりませぬ」
平手は苦虫を噛みつぶしたような顔で、あたしを見た。信長は木刀であたしの顎を持ち上げた。
「貴様の名を聞いてなかったな。名は何と申す」
「……紅」
「紅とな? 変わった名だな。その形は目にあまる。そなたに羽織袴を授けよう。怪我の手当てを受け着替えるがよい」
信長はあたしに背を向け、汚れた足をたらいで洗いその場から立ち去る。
あたしは家臣に支えられ縁側に座り、足を洗い奥座敷に通された。平手は家臣に「もう下がってよい」と告げる。
あたしは痛む足を庇いながら、畳の上に座る。平手はあたしの前にドッカリと腰を降ろした。
「このような変わった身形をした男は初めてじゃ」
平手はあたしのズボンを膝まで捲り上げ、傷の手当てをした。
「男のくせにすね毛もなく、色白でスベスベとした肌じゃのう。筋肉もなく細くて折れそうじゃ。満足に食してないのか」
平手は焼酎を口に含み、傷口にブーッと吹きかけた。