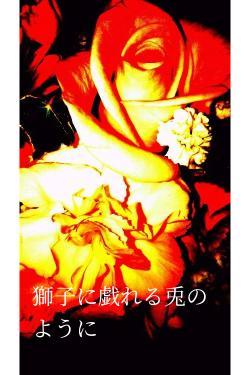「ていうか、信長なんかどうでもいいや」
あたしはその本を学生鞄の中に放り込む。信長には全く興味はなかったが、信也から借りた本を持っていれば、信也と繋がっていられると思ったから。
空腹も満たされ、洋服のままベッドに潜り込み目を閉じる。
初めて男の人に抱かれた。
後悔なんてしていない。
信也の心があたしに向いてなくても、あたしは自分の心に忠実でいたい。
「……すきだよ」
窓から月を見上げそう呟く。
信也に抱かれているような心地よさ。
いつの間にか、深い眠りに落ちた。
◇
「紗紅、起きなさい。またこんなところで食べたの。食べ終わったらちゃんと片付けなさい。ほら、学校に遅れるわよ」
姉にカーテンを開けられ、朝日が狭い部屋に飛び込む。睡眠を邪魔され、あたしの苛々はピークだ。
「……うっせーな。寝かせろよ。学校なんか行かねーよ」
「なに行ってるの。早く起きなさい」
お節介な姉に背を向け、頭から布団を被る。
もし家が裕福な家庭なら、姉は間違いなく名門私立高校に入学していただろう。
高校受験の時、担任から名門私立高校の推薦入試を勧められたが、家庭の経済状況を把握し公立高校を受験した。
当然、姉の成績は学年でトップ。
ギリギリの成績で奇跡的に合格したあたしは、学年最下位に近い。
優等生で自分の夢や希望より、家族や家庭のことを一番に考える姉は、正直ウザイ。
「お弁当、ここに置いとくから、必ず登校しなさいよ。いいわね」
その口調、まるで母親だ。
母と姉が家を出たのを見計らい、あたしはゆっくり体を起こす。
信也はもう起きたかな。
もう仕事しているのかな。
信也に抱かれた夜を思い出し、澄んだ青空と太陽の光がやけに眩しい。
あたしはその本を学生鞄の中に放り込む。信長には全く興味はなかったが、信也から借りた本を持っていれば、信也と繋がっていられると思ったから。
空腹も満たされ、洋服のままベッドに潜り込み目を閉じる。
初めて男の人に抱かれた。
後悔なんてしていない。
信也の心があたしに向いてなくても、あたしは自分の心に忠実でいたい。
「……すきだよ」
窓から月を見上げそう呟く。
信也に抱かれているような心地よさ。
いつの間にか、深い眠りに落ちた。
◇
「紗紅、起きなさい。またこんなところで食べたの。食べ終わったらちゃんと片付けなさい。ほら、学校に遅れるわよ」
姉にカーテンを開けられ、朝日が狭い部屋に飛び込む。睡眠を邪魔され、あたしの苛々はピークだ。
「……うっせーな。寝かせろよ。学校なんか行かねーよ」
「なに行ってるの。早く起きなさい」
お節介な姉に背を向け、頭から布団を被る。
もし家が裕福な家庭なら、姉は間違いなく名門私立高校に入学していただろう。
高校受験の時、担任から名門私立高校の推薦入試を勧められたが、家庭の経済状況を把握し公立高校を受験した。
当然、姉の成績は学年でトップ。
ギリギリの成績で奇跡的に合格したあたしは、学年最下位に近い。
優等生で自分の夢や希望より、家族や家庭のことを一番に考える姉は、正直ウザイ。
「お弁当、ここに置いとくから、必ず登校しなさいよ。いいわね」
その口調、まるで母親だ。
母と姉が家を出たのを見計らい、あたしはゆっくり体を起こす。
信也はもう起きたかな。
もう仕事しているのかな。
信也に抱かれた夜を思い出し、澄んだ青空と太陽の光がやけに眩しい。