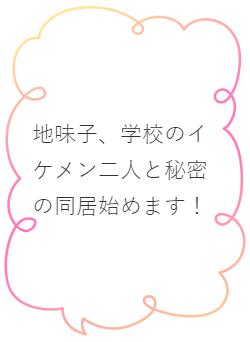「悠、理‥‥‥?何してるの‥‥‥?」
「消毒」
消毒って、どういうこと?
「アイツらに汚い手で触られたから」
何故か、悠理からは答えが返ってくる。
読心術でもあるの?
「だって真紘、全部口に出してるし」
「え!?」
反射的に口を覆う。
「読心術とか、心得てないから」
「‥‥‥‥‥‥」
真顔で返されて、羞恥で顔が赤く染まっていくのが自分でもわかる。
「‥‥‥真紘、震えてる」
「‥‥‥寒いからだよ」
今は7月の初旬。
夏だけど、山のほう、そして夜ということもあり辺りは冷え込んでいる。
そんな中でジャージを脱いだんだから、寒くて震えるに決まってる。
そういうことにする。
「怪我とかしてない?」
「してない」
「もうこれからは、俺から離れないで」
そういって悠理は私の目を見つめる。
いつもとは違って真剣なその目から目が離せなくて。
時が止まったかのように、沈黙が続いた。
‥‥‥って、無理無理。
悠理から離れないとか。
「無理だよ」
そう言おうとした私の口は、悠理の口によって塞がれた。
悠理の顔がドアップになったと思ったら、また遠くなる。
「え、何して‥‥‥」
その続きの言葉は私の口から出ることはなく、またしても悠理の口が私の口を塞ぐ。
ただ、さっきの触れるだけのキスとは違って今度は深い、長い、甘いキス。
私はそんな口付けの中で、意識を失った。
「ん、眩し‥‥‥」
目を開けるとそこは見慣れない天井で。
私はベッドに寝ていて。
そしてすぐ、私の視界はよく知った顔の影によって暗くなる。
「真紘〜!起きた!」
「ひま、り‥‥‥?」
日葵の顔は今にも泣き出しそうだ。
「どうしたの?」
上半身だけ起こして、日葵に尋ねる。
「どうしたのじゃないよ、バカッ!どれだけ心配したと思ってるの!」
「ああ、そう言えば私、さっき‥‥‥。日葵、今何時?」
「次の日の、午前10時だよ!」
私、そんなに眠ってたんだ。
「あれ?だったらなんで日葵、ここにいるの?」
確か合宿のしおりに書いてあった予定表によると、今はお昼ご飯のバーベキューの準備の時間のはずだ。
「なかなか起きない真紘が心配で、相澤くんと狭川くんにバーベキューの用意をしてもらってるの!」
「そうだったんだ‥‥‥」
2人には悪いことをした。
「何があったの!?」
「え、え〜と‥‥‥。どうしても言わなきゃダメ?」
日葵に余計な心配かけたくないから、言いたくないんだけど。
「言って!」
「‥‥‥わかった」
凄い形相の日葵に詰め寄られて、私はとうとう昨日のことを話した。
「消毒」
消毒って、どういうこと?
「アイツらに汚い手で触られたから」
何故か、悠理からは答えが返ってくる。
読心術でもあるの?
「だって真紘、全部口に出してるし」
「え!?」
反射的に口を覆う。
「読心術とか、心得てないから」
「‥‥‥‥‥‥」
真顔で返されて、羞恥で顔が赤く染まっていくのが自分でもわかる。
「‥‥‥真紘、震えてる」
「‥‥‥寒いからだよ」
今は7月の初旬。
夏だけど、山のほう、そして夜ということもあり辺りは冷え込んでいる。
そんな中でジャージを脱いだんだから、寒くて震えるに決まってる。
そういうことにする。
「怪我とかしてない?」
「してない」
「もうこれからは、俺から離れないで」
そういって悠理は私の目を見つめる。
いつもとは違って真剣なその目から目が離せなくて。
時が止まったかのように、沈黙が続いた。
‥‥‥って、無理無理。
悠理から離れないとか。
「無理だよ」
そう言おうとした私の口は、悠理の口によって塞がれた。
悠理の顔がドアップになったと思ったら、また遠くなる。
「え、何して‥‥‥」
その続きの言葉は私の口から出ることはなく、またしても悠理の口が私の口を塞ぐ。
ただ、さっきの触れるだけのキスとは違って今度は深い、長い、甘いキス。
私はそんな口付けの中で、意識を失った。
「ん、眩し‥‥‥」
目を開けるとそこは見慣れない天井で。
私はベッドに寝ていて。
そしてすぐ、私の視界はよく知った顔の影によって暗くなる。
「真紘〜!起きた!」
「ひま、り‥‥‥?」
日葵の顔は今にも泣き出しそうだ。
「どうしたの?」
上半身だけ起こして、日葵に尋ねる。
「どうしたのじゃないよ、バカッ!どれだけ心配したと思ってるの!」
「ああ、そう言えば私、さっき‥‥‥。日葵、今何時?」
「次の日の、午前10時だよ!」
私、そんなに眠ってたんだ。
「あれ?だったらなんで日葵、ここにいるの?」
確か合宿のしおりに書いてあった予定表によると、今はお昼ご飯のバーベキューの準備の時間のはずだ。
「なかなか起きない真紘が心配で、相澤くんと狭川くんにバーベキューの用意をしてもらってるの!」
「そうだったんだ‥‥‥」
2人には悪いことをした。
「何があったの!?」
「え、え〜と‥‥‥。どうしても言わなきゃダメ?」
日葵に余計な心配かけたくないから、言いたくないんだけど。
「言って!」
「‥‥‥わかった」
凄い形相の日葵に詰め寄られて、私はとうとう昨日のことを話した。