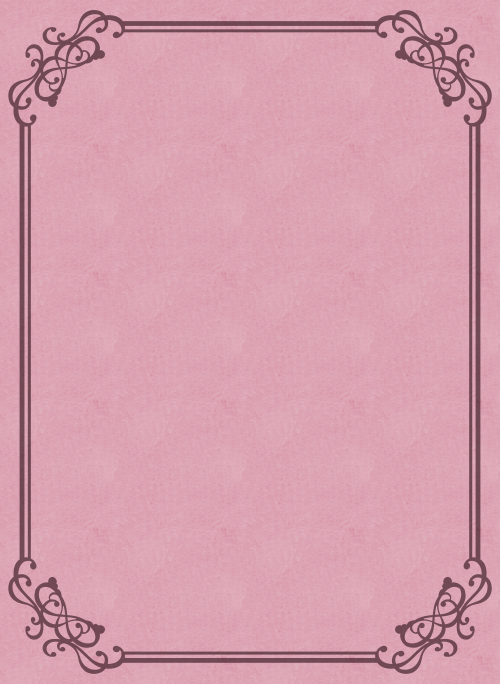「あの人の言っていたこと、この私が信じているとでも?」
ぐすぐすと泣きながら問いかけるソニアに向かい、レオンティーナは胸を張った。当たり前だ。そのくら気づかなくてどうするというのだ。
「あなた達、読み書きはできないんだろうと思っていたわ」
「なぜ、そう思うのです?」
「だって、本がなかったもの。読めるのならば、絵本くらいは置いてあるでしょう」
一昨日、施設を視察に行った時、レオンティーナはそこも素早く見抜いていた。
読み書きを教えているというのであれば、絵本の一冊や二冊、転がっていてもおかしくない。
ここ数十年の間に印刷技術が進んで、安価な絵本が作られるようになっているし、読み書きを復習するのにも必須だからだ。
「――首にしないでください……! 施設長にばれたら、叱られます……!」
「首にはしないって言ってるでしょ。空いた時間、読み書きを教えてくれる人を探すから勉強しなさい。急いで読めるようになりなさいよね。あなたには、私の側についていてもらわないと困るんだから」
「本当ですか?」
ぐすぐすと泣きながら問いかけるソニアに向かい、レオンティーナは胸を張った。当たり前だ。そのくら気づかなくてどうするというのだ。
「あなた達、読み書きはできないんだろうと思っていたわ」
「なぜ、そう思うのです?」
「だって、本がなかったもの。読めるのならば、絵本くらいは置いてあるでしょう」
一昨日、施設を視察に行った時、レオンティーナはそこも素早く見抜いていた。
読み書きを教えているというのであれば、絵本の一冊や二冊、転がっていてもおかしくない。
ここ数十年の間に印刷技術が進んで、安価な絵本が作られるようになっているし、読み書きを復習するのにも必須だからだ。
「――首にしないでください……! 施設長にばれたら、叱られます……!」
「首にはしないって言ってるでしょ。空いた時間、読み書きを教えてくれる人を探すから勉強しなさい。急いで読めるようになりなさいよね。あなたには、私の側についていてもらわないと困るんだから」
「本当ですか?」