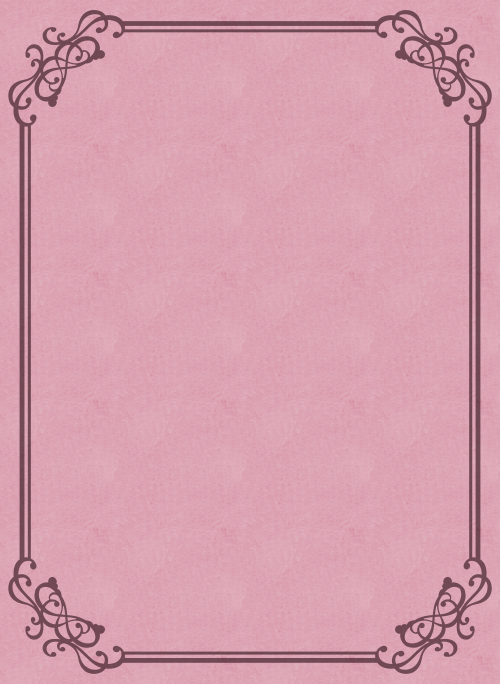まっすぐ処刑台に向かうレオンティーナの視線は揺らがなかった。ただ、目の前を見据え、唇を引き結んだまま歩み続ける――死へと。
(私は、この国の皇妃だから)
たとえ誰に認められなくても。
レオンティーナがかつてこの国の最高位についた女性であった事実は変えようがない。
自分は、何も悪いことなどしていない。
冷たい家庭に生まれ、父にも母にも愛されなかった。夫も同じ。
周囲にいるのは、レオンティーナの財力が目当ての人ばかり。彼らの気を惹くためには、気前よく浪費するしかなかった。
誰かひとりでいい。誰か、レオンティーナを気にとめてくれればきっとそれでよかった。そうしたら、現実から目をそらさないでいられた。
(……腹が立つわよね! 私、そんなに悪いことしたかしら?)
皇妃としては失格だったかもしれない。浪費も、激しかったかもしれない。
けれど、侍女達を無意味に折檻したこともないし、雇い主としてはほどほどだったはずだ。処刑されるほど悪いことをした覚えなどない。
ふつふつと腹の底から込み上げてくるのは、どす黒い怒りにも似た感情。
(私は、この国の皇妃だから)
たとえ誰に認められなくても。
レオンティーナがかつてこの国の最高位についた女性であった事実は変えようがない。
自分は、何も悪いことなどしていない。
冷たい家庭に生まれ、父にも母にも愛されなかった。夫も同じ。
周囲にいるのは、レオンティーナの財力が目当ての人ばかり。彼らの気を惹くためには、気前よく浪費するしかなかった。
誰かひとりでいい。誰か、レオンティーナを気にとめてくれればきっとそれでよかった。そうしたら、現実から目をそらさないでいられた。
(……腹が立つわよね! 私、そんなに悪いことしたかしら?)
皇妃としては失格だったかもしれない。浪費も、激しかったかもしれない。
けれど、侍女達を無意味に折檻したこともないし、雇い主としてはほどほどだったはずだ。処刑されるほど悪いことをした覚えなどない。
ふつふつと腹の底から込み上げてくるのは、どす黒い怒りにも似た感情。