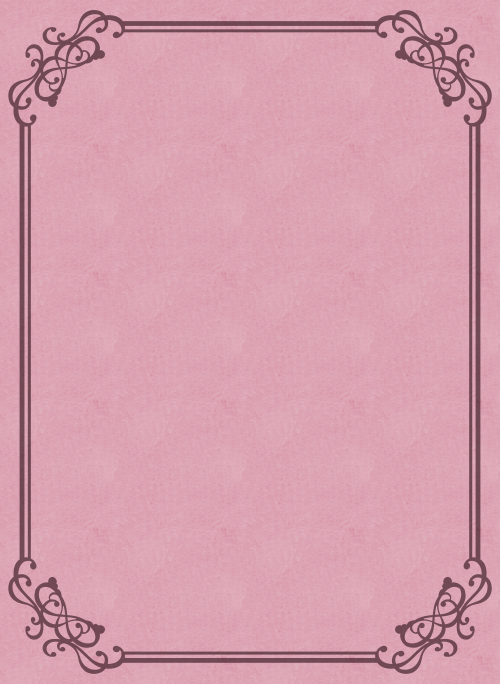ドキドキしているレオンティーナをよそに、母はにっこりと微笑んだ。
「素敵。あなたの勘はあたったわね。お父様が準備してくださったのだけど、この部屋はどうかしら」
「とても素敵よ、お母様。お父様にもお礼を言わなくちゃ」
母にぎゅっと抱き着く。驚いたように、母はぱっと両手を上げた。
前世でも、今の生でも、レオンティーナがこんな風に母に抱き着いたことはない。
「どうかしたの……?」
「いいえ、ただ」
そこでレオンティーナは言葉を切ってしまった。
(言えないわ。お父様とお母様が生きていて嬉しい、なんて)
前世では父は愛人を作り、母は父を呪いながら死んでいった。
この屋敷でひとり、過ごしたのだ――皇宮に嫁ぐまで。
その皇宮も、レオンティーナにとって心安らぐ場とはならなかった。夫に顧みられることないまま、ただ、皇妃という地位だけを与えられた。
(……そうよ、今回は同じ失敗は繰り返さない)
レオンティーナの望みは、至高の座につくことだ。そのために、家は快適な場所でないと困る。
「とても、幸せだと思ったのよ――お母様。だって、一緒にロアに来られたんだもの」
「素敵。あなたの勘はあたったわね。お父様が準備してくださったのだけど、この部屋はどうかしら」
「とても素敵よ、お母様。お父様にもお礼を言わなくちゃ」
母にぎゅっと抱き着く。驚いたように、母はぱっと両手を上げた。
前世でも、今の生でも、レオンティーナがこんな風に母に抱き着いたことはない。
「どうかしたの……?」
「いいえ、ただ」
そこでレオンティーナは言葉を切ってしまった。
(言えないわ。お父様とお母様が生きていて嬉しい、なんて)
前世では父は愛人を作り、母は父を呪いながら死んでいった。
この屋敷でひとり、過ごしたのだ――皇宮に嫁ぐまで。
その皇宮も、レオンティーナにとって心安らぐ場とはならなかった。夫に顧みられることないまま、ただ、皇妃という地位だけを与えられた。
(……そうよ、今回は同じ失敗は繰り返さない)
レオンティーナの望みは、至高の座につくことだ。そのために、家は快適な場所でないと困る。
「とても、幸せだと思ったのよ――お母様。だって、一緒にロアに来られたんだもの」