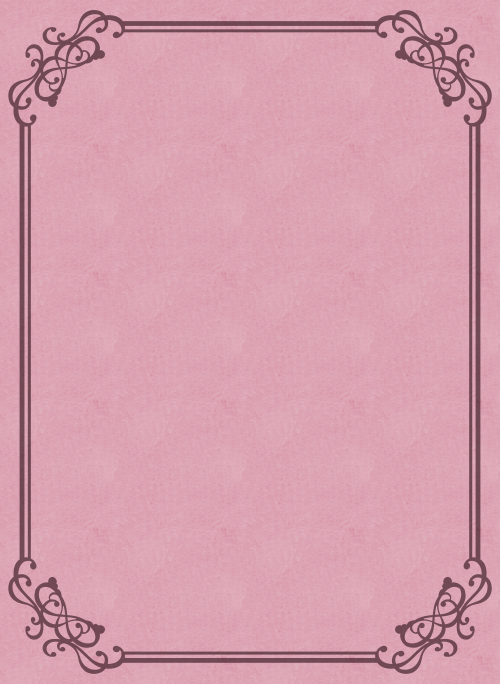牢の扉をノックし、中に入ってきたのは、レオンティーナの身の回りの世話をしている娘だ。ソニアという名前で、親を亡くした子供を養育する施設の出身だそうだ。
「……最後の食事というわけね」
明日の朝、レオンティーナは処刑されることになっている。盆にのせられていたのは、仮にも一国の皇妃であった女性に出す最後の晩餐としては、あまりにも質素なものだった。
「またマレイモのスープ? せめて、パンはつかないの」
「ごめんなさい、レオンティーナ様。皇帝陛下が亡くなっても、国の借金を返せるわけじゃないし……レオンティーナ様にまで、あまりお金を割けないんですよ」
そう言って頭を下げるソニアは、心から申し訳なさそうに見える。ここでの食事を彼女が決めているわけでもないのに。
「まあ、いいわ。空腹のままってわけにもいかないものね」
「明日の朝は――湯あみは無理ですけど。お湯をお持ちしますから、お顔を洗って、お髪を整えましょうね」
「――悪いわね」
そう返し、レオンティーナは牢の中を見回す。
(……これが最後の晩餐だなんてね)
レオンティーナの脳裏によぎるのは、華やかな皇宮での日々。
「……最後の食事というわけね」
明日の朝、レオンティーナは処刑されることになっている。盆にのせられていたのは、仮にも一国の皇妃であった女性に出す最後の晩餐としては、あまりにも質素なものだった。
「またマレイモのスープ? せめて、パンはつかないの」
「ごめんなさい、レオンティーナ様。皇帝陛下が亡くなっても、国の借金を返せるわけじゃないし……レオンティーナ様にまで、あまりお金を割けないんですよ」
そう言って頭を下げるソニアは、心から申し訳なさそうに見える。ここでの食事を彼女が決めているわけでもないのに。
「まあ、いいわ。空腹のままってわけにもいかないものね」
「明日の朝は――湯あみは無理ですけど。お湯をお持ちしますから、お顔を洗って、お髪を整えましょうね」
「――悪いわね」
そう返し、レオンティーナは牢の中を見回す。
(……これが最後の晩餐だなんてね)
レオンティーナの脳裏によぎるのは、華やかな皇宮での日々。