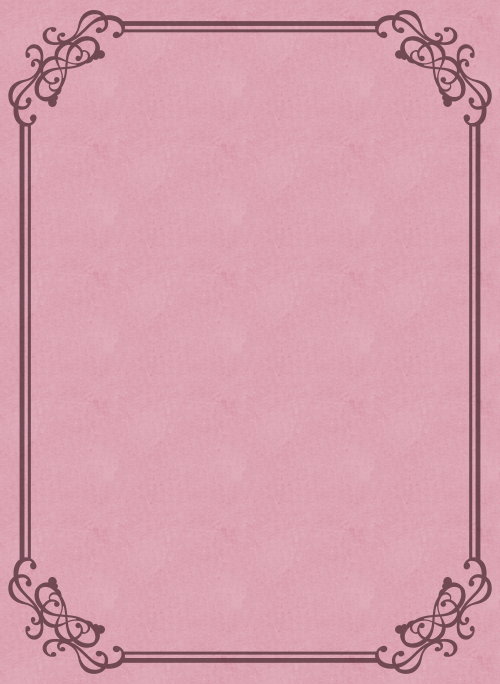白に銀で植物模様を刺繍したドレスを身にまとったレオンティーナは、緊張の面持ちで皇宮に入った。
「――ティーナ! 今日も君はとても綺麗だ」
「ヴィルヘルム様……急にお口が上手になったのではないですか?」
レオンティーナを待ち構えたヴィルヘルムは、レオンティーナの困惑には構わずこちらに突進してきた。
レオンティーナの手を取り、そこに唇を落とす。そして、改めてレオンティーナと向き合った。
「そんなんじゃない。俺は、本当のことしか口にしない」
黒い髪に白いドレスはよく映えていて、まるで月の女神のようにも見えるとは支度をしてくれたソニアの言葉だ。
「……ヴィルヘルム様も、とても素敵……ですけど!」
ヴィルヘルムの顔を見ることができないのは、どうしたって、彼にすくわれたことを思い出さずにはいられないからだ。
(まさか、こんなにも好きになるなんて思ってもいなかった)
知り合ったばかりの頃は、ヴィルヘルムは頼りなく見えていた。それなのに、今はこんなにもレオンティーナをドキドキさせる。
人というものは、本当にわからない。
(……いえ、私も変わったもの)
「――ティーナ! 今日も君はとても綺麗だ」
「ヴィルヘルム様……急にお口が上手になったのではないですか?」
レオンティーナを待ち構えたヴィルヘルムは、レオンティーナの困惑には構わずこちらに突進してきた。
レオンティーナの手を取り、そこに唇を落とす。そして、改めてレオンティーナと向き合った。
「そんなんじゃない。俺は、本当のことしか口にしない」
黒い髪に白いドレスはよく映えていて、まるで月の女神のようにも見えるとは支度をしてくれたソニアの言葉だ。
「……ヴィルヘルム様も、とても素敵……ですけど!」
ヴィルヘルムの顔を見ることができないのは、どうしたって、彼にすくわれたことを思い出さずにはいられないからだ。
(まさか、こんなにも好きになるなんて思ってもいなかった)
知り合ったばかりの頃は、ヴィルヘルムは頼りなく見えていた。それなのに、今はこんなにもレオンティーナをドキドキさせる。
人というものは、本当にわからない。
(……いえ、私も変わったもの)