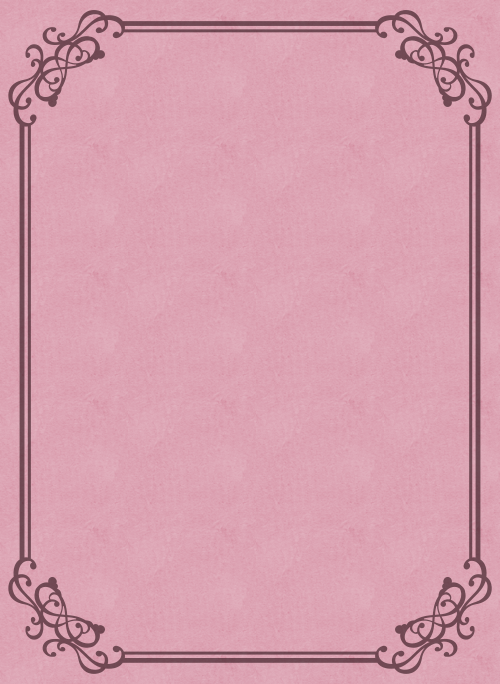自分の足が、がくがくとしていることにレオンティーナはその時初めて気が付いた。
(……目の前で、命のやり取りがあるのは初めてじゃなかったのに)
目の前で、血を流しながら倒れていく騎士を何人見送っただろう。
皇妃であるというそれだけで、レオンティーナを守るために力を尽くしてくれた人達がいた。
あの時は、それが当然だと思っていた――なんて、傲慢だったのだろう。
(私は……私が、皇帝になるなんて、いいの?)
「大丈夫だ。俺がついている」
ヴィルヘルムの腕が、そっと身体に回される。レオンティーナは静かに目を閉じた。
「よし――行くか」
けれど、ヴィルヘルムの腕に包み込まれていたのは一瞬のことだった。彼はすぐにレオンティーナを離すと、側に倒れていた男性を引きずり上げる。
「私、この人見たことあるわ……」
レオンティーナは、呆然としてつぶやいた。
そこにいたのは、皇妃の侍従だった。いつだったか、皇妃の前までレオンティーナを案内した使用人だ。
(……そうね。皇妃の侍従なら)
(……目の前で、命のやり取りがあるのは初めてじゃなかったのに)
目の前で、血を流しながら倒れていく騎士を何人見送っただろう。
皇妃であるというそれだけで、レオンティーナを守るために力を尽くしてくれた人達がいた。
あの時は、それが当然だと思っていた――なんて、傲慢だったのだろう。
(私は……私が、皇帝になるなんて、いいの?)
「大丈夫だ。俺がついている」
ヴィルヘルムの腕が、そっと身体に回される。レオンティーナは静かに目を閉じた。
「よし――行くか」
けれど、ヴィルヘルムの腕に包み込まれていたのは一瞬のことだった。彼はすぐにレオンティーナを離すと、側に倒れていた男性を引きずり上げる。
「私、この人見たことあるわ……」
レオンティーナは、呆然としてつぶやいた。
そこにいたのは、皇妃の侍従だった。いつだったか、皇妃の前までレオンティーナを案内した使用人だ。
(……そうね。皇妃の侍従なら)