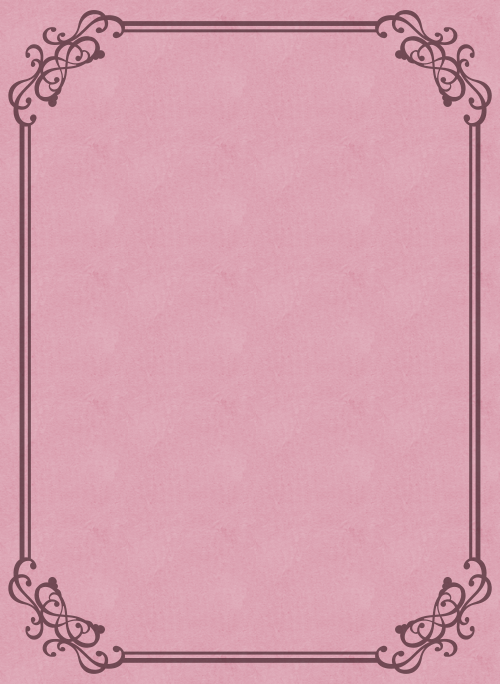レオンティーナは、まっすぐにヴィルヘルムを見つめた。
今、レオンティーナが考えていることを言葉にしたら、ヴィルヘルムはどんな反応を返すのだろう。
ひょっとしたら、彼との友情――そしてそれ以上の感情も――ここまでになるのかもしれなかった。
「私は、皇帝になるつもり――でした。この国は弱体化しているから……誰か、手を打つべきだと、そう思ったんです」
一笑に付されてもしかたないほど、それは、途方もない夢だった。
この国に、かつて女帝が立ったという例はない。レオンティーナは、大公家の娘ではあっても、目指すならば皇妃という立場にあった。
たしかに、レオンティーナが行動を始めた八歳の頃。この国にはあちこち弱体化の芽が見えていた。
だが、アルニム熱については、レオンティーナがニナ草の栽培方法の開発者を見つけ出したことで回避した。
ケルスティンが死亡しなかったことで、皇宮の勢力図もレオンティーナの知る者とは変化した。
今、レオンティーナが考えていることを言葉にしたら、ヴィルヘルムはどんな反応を返すのだろう。
ひょっとしたら、彼との友情――そしてそれ以上の感情も――ここまでになるのかもしれなかった。
「私は、皇帝になるつもり――でした。この国は弱体化しているから……誰か、手を打つべきだと、そう思ったんです」
一笑に付されてもしかたないほど、それは、途方もない夢だった。
この国に、かつて女帝が立ったという例はない。レオンティーナは、大公家の娘ではあっても、目指すならば皇妃という立場にあった。
たしかに、レオンティーナが行動を始めた八歳の頃。この国にはあちこち弱体化の芽が見えていた。
だが、アルニム熱については、レオンティーナがニナ草の栽培方法の開発者を見つけ出したことで回避した。
ケルスティンが死亡しなかったことで、皇宮の勢力図もレオンティーナの知る者とは変化した。