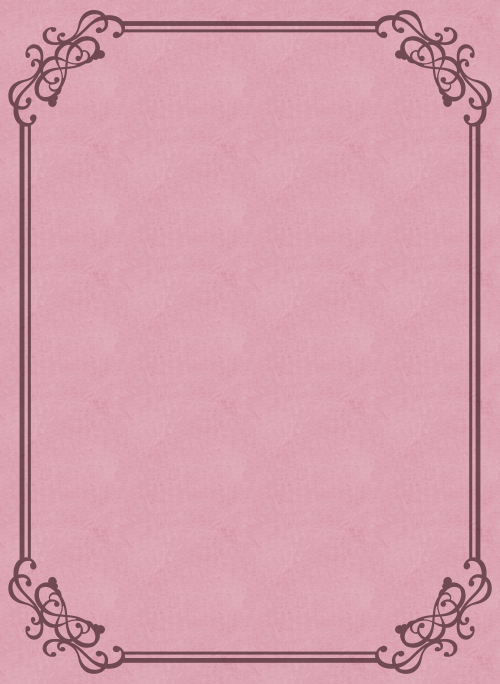ヴィルヘルムと自分の間にある高い壁を、どうやって乗り越えたらいいのかわからない。
自分が皇帝になるしかないと思っていた。
けれど、ヴィルヘルムは前世の心の優しさはそのままに、前世は持ち合わせていなかった強さまで持つ青年に成長した。
(――それならいっそ、ヴィルヘルム様にお任せした方がいいんじゃないの……?)
ヴィルヘルムを側で支える忠実な家臣となる。そんな未来を最近では思い浮かべるようになった。
レオンティーナにその資格があるかどうかはわからないけれど。
「――お茶を用意しましょうか」
「ええ、お願い」
レオンティーナが、ソニアに答えを返した時だった。
窓の外から、屋敷に向けて全力疾走してくる馬車が見えた。
(あら、あの馬車は……)
どこの馬車か見てとったとたん、レオンティーナは血の気が引くような気がした。
あの馬車につけられているのは、皇帝一族の紋章だ。
「ソニア!」
レオンティーナの声の鋭さに、ソニアもただ事ではないとすぐに理解したようだ。
「かしこまりました!」
自分が皇帝になるしかないと思っていた。
けれど、ヴィルヘルムは前世の心の優しさはそのままに、前世は持ち合わせていなかった強さまで持つ青年に成長した。
(――それならいっそ、ヴィルヘルム様にお任せした方がいいんじゃないの……?)
ヴィルヘルムを側で支える忠実な家臣となる。そんな未来を最近では思い浮かべるようになった。
レオンティーナにその資格があるかどうかはわからないけれど。
「――お茶を用意しましょうか」
「ええ、お願い」
レオンティーナが、ソニアに答えを返した時だった。
窓の外から、屋敷に向けて全力疾走してくる馬車が見えた。
(あら、あの馬車は……)
どこの馬車か見てとったとたん、レオンティーナは血の気が引くような気がした。
あの馬車につけられているのは、皇帝一族の紋章だ。
「ソニア!」
レオンティーナの声の鋭さに、ソニアもただ事ではないとすぐに理解したようだ。
「かしこまりました!」