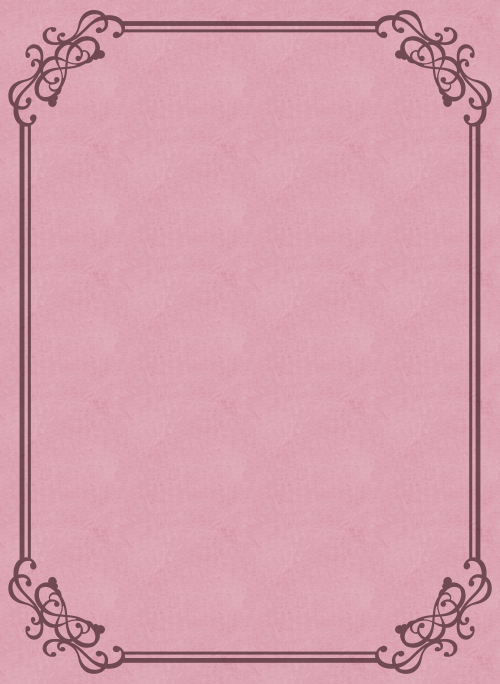手近にあったのはカーテンだけ。その中に逃げ込み、ぐるぐると巻き付けて顔だけ出した。
「……女性の部屋を訪問するには遅すぎる時間ですね!」
「――ごめん。でも、どうしても伝えておきたくて。だって――手を打ったとしても、俺が皇妃の手を逃れられるとは限らない」
「そんなこと言わないで……!」
そんな縁起でもない想像をしないでほしい。手を差し伸べたいけれど、カーテンを巻き付けてしまっているから手を出すこともできなかった。
泣きそうな顔になっていると、ヴィルヘルムはいたずらめいた笑みを浮かべた。
「あとひとつ、君は間違えていることがある」
「――なんでしょう?」
首を傾げたら、不意にヴィルヘルムの唇が、レオンティーナの唇に触れる。
それは、ほんの一瞬のことで、抵抗する間もなかった。
もうだめだ。こんなにも顔が熱くなっている。ただ、瞬きを繰り返した。
「――ごめん」
「あ、謝るくらいなら、最初からしないでっ!」
ヴィルヘルムの顔を見ていると、どうしても泣きそうになってしまう。
こんな風に過ごしたかったわけじゃないのに。
「ティーナ」
「……女性の部屋を訪問するには遅すぎる時間ですね!」
「――ごめん。でも、どうしても伝えておきたくて。だって――手を打ったとしても、俺が皇妃の手を逃れられるとは限らない」
「そんなこと言わないで……!」
そんな縁起でもない想像をしないでほしい。手を差し伸べたいけれど、カーテンを巻き付けてしまっているから手を出すこともできなかった。
泣きそうな顔になっていると、ヴィルヘルムはいたずらめいた笑みを浮かべた。
「あとひとつ、君は間違えていることがある」
「――なんでしょう?」
首を傾げたら、不意にヴィルヘルムの唇が、レオンティーナの唇に触れる。
それは、ほんの一瞬のことで、抵抗する間もなかった。
もうだめだ。こんなにも顔が熱くなっている。ただ、瞬きを繰り返した。
「――ごめん」
「あ、謝るくらいなら、最初からしないでっ!」
ヴィルヘルムの顔を見ていると、どうしても泣きそうになってしまう。
こんな風に過ごしたかったわけじゃないのに。
「ティーナ」