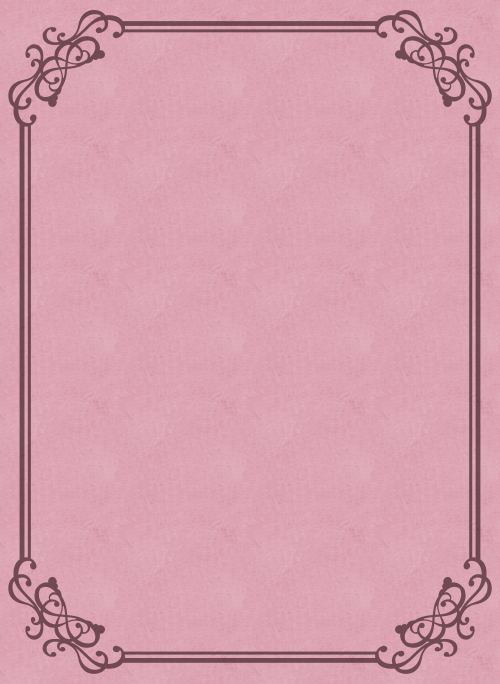今日、皇妃との間にあったことをぽつぽつと話す。
もちろん、前世の知識があったから暗殺に思い至ったなんて話はしなかったけれど、レオンティーナの不安を父も感じ取ったようだった。
〝手を打つ〟が単なる脅しであればよいのだが、そうでない可能性も大いにある。
「そういうことなら、私からヴィルヘルム殿下にお伝えしよう。殿下には、政務でお会いすることもある。お前が皇宮に行くより、その方が怪しまれないですむ」
こんなにも胸が痛むのは――ヴィルヘルムに惹かれているから、だろうか。
ソニアが言うように、ヴィルヘルムに恋をしているのだろうか。
(だけど、私は……)
ぐっと唇をかみしめたけれど、目のあたりがじんわりと熱くなってくる。
皇帝の座を目指そうと思っていたのに――立ち止まっているわけにはいかないのに。
それなのに、一度気づいてしまえば、ヴィルヘルムへの気持ちが、どんどん膨れ上がり、爆発しそうになる。
「しかし、困ったことになったものだね。ティーナ、私は、君が一番望むようにしたいと思っているよ。君はどうしたい? 君の結婚についても、だよ」
もちろん、前世の知識があったから暗殺に思い至ったなんて話はしなかったけれど、レオンティーナの不安を父も感じ取ったようだった。
〝手を打つ〟が単なる脅しであればよいのだが、そうでない可能性も大いにある。
「そういうことなら、私からヴィルヘルム殿下にお伝えしよう。殿下には、政務でお会いすることもある。お前が皇宮に行くより、その方が怪しまれないですむ」
こんなにも胸が痛むのは――ヴィルヘルムに惹かれているから、だろうか。
ソニアが言うように、ヴィルヘルムに恋をしているのだろうか。
(だけど、私は……)
ぐっと唇をかみしめたけれど、目のあたりがじんわりと熱くなってくる。
皇帝の座を目指そうと思っていたのに――立ち止まっているわけにはいかないのに。
それなのに、一度気づいてしまえば、ヴィルヘルムへの気持ちが、どんどん膨れ上がり、爆発しそうになる。
「しかし、困ったことになったものだね。ティーナ、私は、君が一番望むようにしたいと思っているよ。君はどうしたい? 君の結婚についても、だよ」