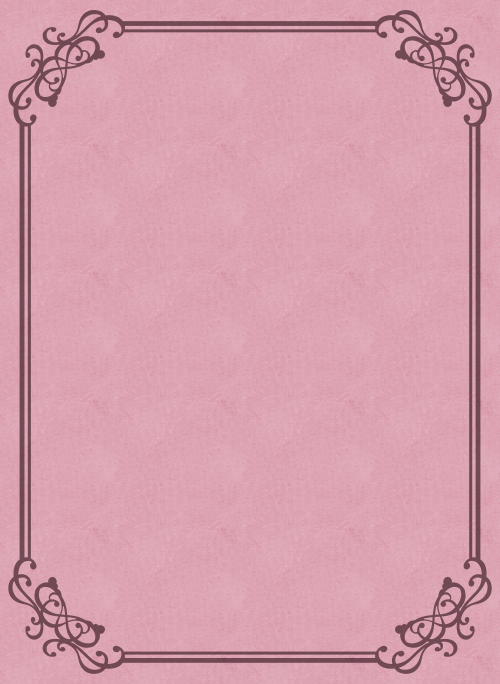「べ、別にそういうわけでは……ただ、ルイーザ殿下と仲良くさせていただいていますから」
あの舞踏会以来、レオンティーナに近づく令嬢も増えた。
レオンティーナの側にいれば、皇族の覚えがめでたくなるということに気付いたのだろう。そういう女性の動きは、前世でも今回の生でも変わらないようだ。
彼女達にレオンティーナは取り合わないようにしていたけれど、それでも噂というのは広まるものだ。
皇宮で開かれていた茶会に出席し、笑顔で令嬢達をやり過ごしたレオンティーナは、帰りの馬車でぐったりしてしまった。
「皆、私とヴィルヘルム様のことを気にし過ぎじゃない?」
「……私も気になりますよ、お嬢様」
「笑い事じゃないわ……これからが、大切な時期なのに」
馬車で待っていたソニアはくすくす笑っているけれど、レオンティーナはぼやいた。
これから、自分の味方を増やしていかないといけない時期なのだ。それなのに、恋愛沙汰に巻き込まれるなんてごめんだ――いや、巻き込まれてはならないのだ。自分にそう言い聞かせる。
「――でも、私の目には、ヴィルヘルム殿下が一番お好きなように見えますけど」
あの舞踏会以来、レオンティーナに近づく令嬢も増えた。
レオンティーナの側にいれば、皇族の覚えがめでたくなるということに気付いたのだろう。そういう女性の動きは、前世でも今回の生でも変わらないようだ。
彼女達にレオンティーナは取り合わないようにしていたけれど、それでも噂というのは広まるものだ。
皇宮で開かれていた茶会に出席し、笑顔で令嬢達をやり過ごしたレオンティーナは、帰りの馬車でぐったりしてしまった。
「皆、私とヴィルヘルム様のことを気にし過ぎじゃない?」
「……私も気になりますよ、お嬢様」
「笑い事じゃないわ……これからが、大切な時期なのに」
馬車で待っていたソニアはくすくす笑っているけれど、レオンティーナはぼやいた。
これから、自分の味方を増やしていかないといけない時期なのだ。それなのに、恋愛沙汰に巻き込まれるなんてごめんだ――いや、巻き込まれてはならないのだ。自分にそう言い聞かせる。
「――でも、私の目には、ヴィルヘルム殿下が一番お好きなように見えますけど」