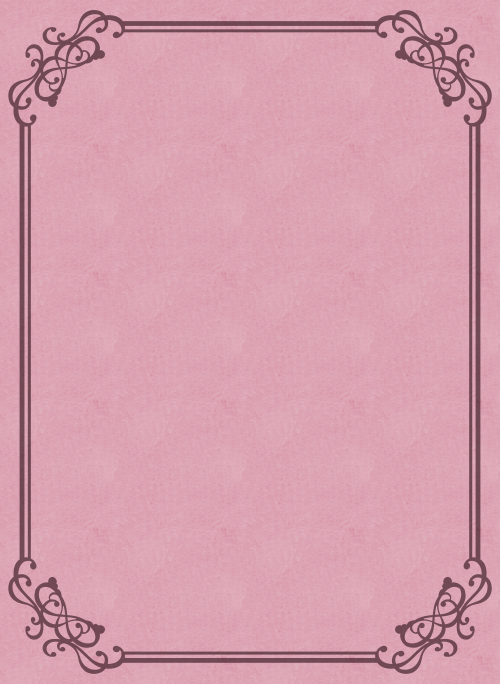愛妾はもうひとりいて、そちらには皇子がひとり、皇女がふたりいる。
子供の数は優劣にはつながらないだろうが、自分の子供が皇位を継ぐか否かは大問題だ。
(たしかに、皇妃からしたら、愛妾の息子であるヴィルヘルム殿下と私が近づくのは面白くないかも)
父に言われ、初めてその可能性に思い至ったのは、レオンティーナのうかつなところかもしれない。
だが、前世でアンドレアスがレオンティーナを娶ったのはいやいやだったから、彼の方から近づいてくるなんてまったく思っていなかったのだ。
「気が進まないわ。だって、今は勉強したいことが山のようにあるんだもの。皇子妃になるための勉強はしたくありません」
「そうだなぁ……ティーナには、好きに生きてもらいたいからね。ティーナが気が進まないというのなら、無理に進める必要もないだろう」
皇妃からの申し入れを断るということは、大公家にとっては不利益となる可能性が大きい。
それなのに、父は、レオンティーナの意思を尊重してくれるのだという。
(今のお父様は……好きだわ。お母様も)
子供の数は優劣にはつながらないだろうが、自分の子供が皇位を継ぐか否かは大問題だ。
(たしかに、皇妃からしたら、愛妾の息子であるヴィルヘルム殿下と私が近づくのは面白くないかも)
父に言われ、初めてその可能性に思い至ったのは、レオンティーナのうかつなところかもしれない。
だが、前世でアンドレアスがレオンティーナを娶ったのはいやいやだったから、彼の方から近づいてくるなんてまったく思っていなかったのだ。
「気が進まないわ。だって、今は勉強したいことが山のようにあるんだもの。皇子妃になるための勉強はしたくありません」
「そうだなぁ……ティーナには、好きに生きてもらいたいからね。ティーナが気が進まないというのなら、無理に進める必要もないだろう」
皇妃からの申し入れを断るということは、大公家にとっては不利益となる可能性が大きい。
それなのに、父は、レオンティーナの意思を尊重してくれるのだという。
(今のお父様は……好きだわ。お母様も)