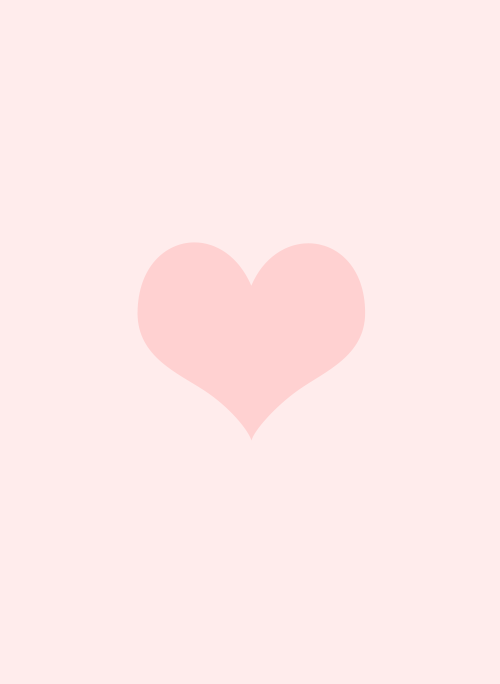だけど、千尋が帰って、1人になると悲しさと寂しさがこみ上げて来る。
(なんでなんだろうな・・・なんでこんなに思いって伝わらないんだろうな・・・。)
子供の頃から、大好きなのに、でもいくら片方だけが想ってても、どうにもならないんだよね。私だって、小笠原さんにあんなに想ってもらってるのに、やっぱり・・・。
恋って理不尽、本当に理不尽・・・。私の目にジワッとまた涙が滲んで来た時だ。
「失礼します。」
の声と共に、ドアが開く。そして入って来た人の姿を見て、私は息を飲み、次の瞬間、思わず顔を背けてしまった。
「夕飯、済んだか?」
一方、何事もなかったかのように澤城くんは尋ねて来る。
「うん。」
彼の顔を見ないまま、私は頷いた。
「じゃ、よかったらデザート代わりに、これ、食べてくれねぇか?」
その言葉に、私は彼の方に目を向けた。彼の手にはキレイにリボンが掛かった小さな包みが。
何?って視線で問い掛けた私に
「開けてみてくれ。」
と言いながら、手渡す。受け取った私はベッドのテーブルにそれを置くと、リボンを解き、蓋を開けた。そこから現れたのは
「ケーキ・・・。」
本当に1人分にカットされた、お店で普通に売っている大きさのひと切れのケーキだった。
「思ったより時間掛かっちまった。ケーキ焼いたの、久しぶりだったから。」
「えっ、これ澤城くんが焼いたの?」
「ああ、婆ちゃん直伝のチョコレートケーキ。バレンタインだろ、今日。だったらやっぱりチョコかなと思って。」
そう言って、照れ臭そうに笑った澤城くんは、一回私から、箱を受け取って、お皿に移すと、フォークと一緒に私に差し出した。
「食べてみてくれ。自分で味見した限りでは、結構イケてると思う。」
「うん、いただきます。」
私はそう言うと、一口、口に運ぶ。そして
「美味しい・・・。」
思わず、そう言って顔がほころぶ。
「よかった。」
澤城くんも、ホッとしたように笑顔になる。
「初めてこれを婆ちゃんに習った時、こう言われた。『いつか、大切な人が出来たら、食べさせてあげな。このケーキは、亡くなったおじいちゃんが大好きだったんだ』って。」
その澤城くんの言葉に、私は思わず顔を上げた。
(なんでなんだろうな・・・なんでこんなに思いって伝わらないんだろうな・・・。)
子供の頃から、大好きなのに、でもいくら片方だけが想ってても、どうにもならないんだよね。私だって、小笠原さんにあんなに想ってもらってるのに、やっぱり・・・。
恋って理不尽、本当に理不尽・・・。私の目にジワッとまた涙が滲んで来た時だ。
「失礼します。」
の声と共に、ドアが開く。そして入って来た人の姿を見て、私は息を飲み、次の瞬間、思わず顔を背けてしまった。
「夕飯、済んだか?」
一方、何事もなかったかのように澤城くんは尋ねて来る。
「うん。」
彼の顔を見ないまま、私は頷いた。
「じゃ、よかったらデザート代わりに、これ、食べてくれねぇか?」
その言葉に、私は彼の方に目を向けた。彼の手にはキレイにリボンが掛かった小さな包みが。
何?って視線で問い掛けた私に
「開けてみてくれ。」
と言いながら、手渡す。受け取った私はベッドのテーブルにそれを置くと、リボンを解き、蓋を開けた。そこから現れたのは
「ケーキ・・・。」
本当に1人分にカットされた、お店で普通に売っている大きさのひと切れのケーキだった。
「思ったより時間掛かっちまった。ケーキ焼いたの、久しぶりだったから。」
「えっ、これ澤城くんが焼いたの?」
「ああ、婆ちゃん直伝のチョコレートケーキ。バレンタインだろ、今日。だったらやっぱりチョコかなと思って。」
そう言って、照れ臭そうに笑った澤城くんは、一回私から、箱を受け取って、お皿に移すと、フォークと一緒に私に差し出した。
「食べてみてくれ。自分で味見した限りでは、結構イケてると思う。」
「うん、いただきます。」
私はそう言うと、一口、口に運ぶ。そして
「美味しい・・・。」
思わず、そう言って顔がほころぶ。
「よかった。」
澤城くんも、ホッとしたように笑顔になる。
「初めてこれを婆ちゃんに習った時、こう言われた。『いつか、大切な人が出来たら、食べさせてあげな。このケーキは、亡くなったおじいちゃんが大好きだったんだ』って。」
その澤城くんの言葉に、私は思わず顔を上げた。