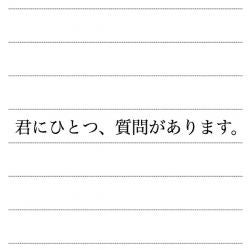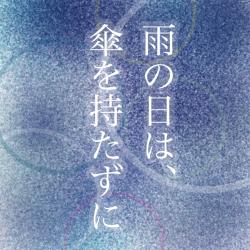「あなた、俺の名前知ってます?」
「え、し、知りませんけど……」
おにぎりをかじりながら唐突に彼女に質問をしてみれば、怪訝そうな顔で返答をされた。
その答えに当たり前だと思いつつ、思わず笑みが溢れる。
「じゃあ、年齢」
「いや、知ってたら怖いですよね」
「ごもっとも」
「え、おちょくってます!?」
「いや、なにも知らない男にこんなに良くして、俺がやばいやつだったらとか思わないのかなと思って」
そう言った俺を、きょとんとした表情で見つめる彼女。フリーズしたまま動かないその姿に俺はなにか間違ったことでも言っただろうかと思わず、つられてフリーズした。
「お兄さんがやばいやつなわけないです」
「……」
きっぱり、言い切った彼女の声音は真っ直ぐで、
「やばいやつなら、電車で声をかけた段階で私の行為に付け上がって色々要求してくるはずです。でもお兄さんは体調悪いくせに、遠慮したじゃないですか」
油断していた、俺の胸にグサリと突き刺さった。