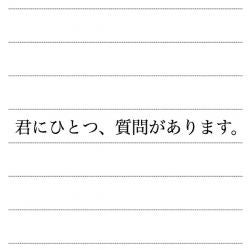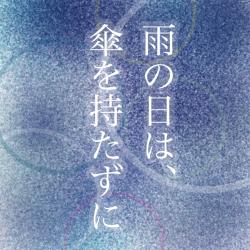俺は察しはいい方だと思う。
要するにこういうことだ。
「つまり君は、俺と食事に行きたいと?」
「はい!お食事しながらお話しできればと!もちろんお仕事の話も」
お食事に行きたい感を前面に出され、仕事はついでだろうにとこの状況なら誰もが思うだろう。
「ダメですか?」
「……」
うるうるな瞳でこちらを見てくるその女。可愛いと思ってやっているんだろうな、きっと。俺は口角を上げてにこやかに微笑んでみせた。
「すまないがまだ仕事が残っているから」
「えー、そうなんですか?でしたらお仕事お手伝いしますよ」
「いいや、そんなことはさせられないよ」
「え、でも私にできることなら」
「(君には無理だよ)」
「ふたりでやったほうが早いですよね」
「(いや、多分俺ひとりのほうが早く終わる)」
「それに、遅くなっても私は大丈夫ですよ」
「(香水くさいし、髪巻き過ぎだろ。何しに会社に来てるんだ)」
「ね、華井専務」
目の前の女を視界に入れながら、早く胡桃に会いたい。そう思った。
キンキン響く高い声も、綺麗に描かれた眉毛も、真っ赤なリップも、ばっちり巻かれた髪も、付け過ぎな香水もどれも俺の好みじゃない。
「気持ちだけ受け取っておくよ」
「……そんな」
なかなか諦めてくれない女をどうにかこうにか説得し、帰るように促した。
仕事が残っているというのに今のでどっと疲れが溜まった。
机の上に積まれた資料やプレゼン用紙の山を目にして思わずため息を溢す。