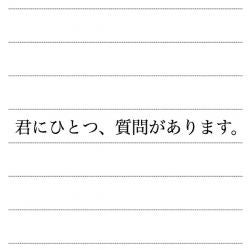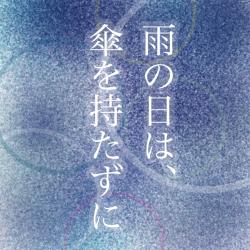「だから、帰るよ。なんなら今日はもうやめよう。皐月くんお仕事で疲れてると思うしせっかくの休日、私に使ったらもったいな……」
「お前、バカだろ」
「え、」
言い終わる前に皐月くんの言葉に遮られた私の声は音になることなく消えていった。
掴まれた右手を引かれた私は、温かい皐月くんの体温に捕らわれる。
「お前のせいだ」
「だから、帰る……」
「そうじゃなくて」
「じゃあ、なにさ……」
ぎゅっと皐月くんに抱きしめられた体が温かくて、でもしんどい。
「皐月、くん?」
「今日、俺の家で映画観たあとどっか行くのか?」
「え、いや、どこも行かないけど」
想像もしていなかった皐月くんの質問に、腕の中で皐月くんの横顔をちらりと盗み見る。
すると、ゆっくりと腕を解いてくれた皐月くんは、コツンと自分のおでこを私のおでこにぶつけてきた。
近いよ皐月くん。いったいどうしたんだろう。