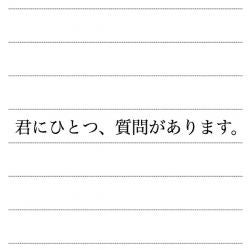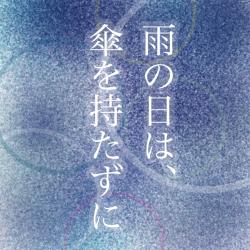「もしかして、一緒にご飯食べれないの気にしてくれてたの?」
「うるさい、そんなわけないだろバカ」
スーツのジャケットを脱ぎなら耳を赤に染めた皐月くん。
「あ、皐月くん照れてる。さっきは待ってなくていいとか言ってたのに」
「うるさい」
「照れてるの?」
「(明日も学校なのに遅い時間まで待たせるわけにはいかないだろ)」
「向かえも来るなとか言ったのに」
「いいから黙って食ってろ」
「はーい」
「(こんな遅い時間にひとりで外歩かせるとか無理だから)」
「じゃあ、私さっき言った抹茶味」
「バカ」
「え、」
「俺が両方食いたくて買ったんだから全部食うな半分ずつにしろ」
「え、イチゴも抹茶も食べていいの?」
「だから、俺が両方食いたいの」
「(皐月くんの優しさは不器用だ)」
皐月くんの夜ご飯と一緒に入っていたのは、カップに入ったアイスクリームだった。
私は皐月くんがご飯を食べている横で、イチゴ味と、抹茶味のアイスを木のスプーンでつついた。半分は皐月くんにとっておくことにする。
「皐月くん、イチゴ味好きなの?私はいちばんイチゴ味が好きだよ」
「うるさい、黙って食ってろ」
「そんな怒らなくていいじゃん」
「(お前が好きだから買ってきたんだろ)」
「好きなくせに」
「本当にうるさい、それとちゃんと髪乾かしてから来いよ。風邪ひくだろ」
「うん、ありがとう。アイスもありがとう」
大きな皐月くんの掌が頭にかけていたタオルの上から少し乱暴にクシャクシャと私の髪を撫でた。
「(飯、誘ってくれてありがとう)」