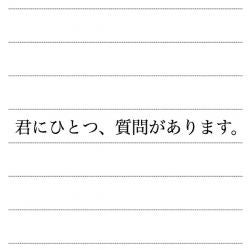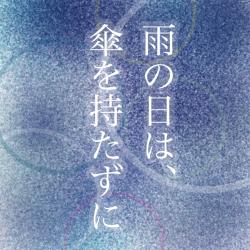「胡桃」
「え、ちょ、皐月くん!?」
するりと胡桃の隙をついて、手首を引いて抱き寄せる。胡桃はいつだって甘い匂いがして、俺の理性を乱して、思考回路を鈍らせる。
ガチャリと後ろで鈍い音を立てて扉が閉まった。
無性に、会いたかった。抱きしめたかった。
「皐月くん、ねぇ、離して」
「無理」
「お水持ってくるから」
「嫌だ」
「ねぇ、だいぶ酔ってるでしょ?大丈夫?」
「……」
華奢な身体をぎゅっと、壊れないように大切に、大切に抱きしめる。
よかった。胡桃は俺が完全に酔っ払っていると思ってくれているみたいだ。だったら、とことん卑怯に酒の力を借りてやる。
「皐月くんって、お酒飲むと甘えたになるの?」
「そーかも」
「なんか、可愛い」
「可愛いって言うな」
「ごめんなさい」
「……」
「……」
「胡桃、会いたかったよ」
「普段の皐月くんはそんなこと言わないよ」
「そー?」
「うん。言わないよ。そんなこと言うなんて絶対酔ってるよ」
「そうかも、」
「そうかもじゃないよ」
「酔いが覚めるまでもう少し、こうさせて」
「(どうせ明日になったら今日言ったこと全部忘れてるんだろうな……)」
「(君にどうしても会いたいなんて、酔ったフリでもしなきゃ、こんなこと言えない)」
ずるい大人で、