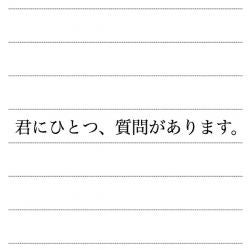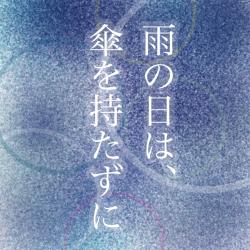「もしかして、皐月くん心配して来てくれたの?」
「バカ、違う」
「あ、照れてる!」
「うるさい、さっさと寝ろ」
「ねぇ、でも顔真っ赤だよ」
「お前、いい加減にしないと雷の下に突き出すぞ」
「鬼!」
「嫌だったら黙って寝ろ」
真っ赤になった皐月くんに布団をかぶせられ、私の震えは止まっていた。
ベッドの上で横になり、ラグマットの上に座りながら髪を拭く皐月くんを見つめる。今度は私が見上げる形になった。
「ねぇ、皐月くん。私が寝たら皐月くんは自分の家に帰るの?」
「当たり前だろ」
「そっか……そうだよね」
「……」
「ねぇ、皐月くん」
「……」
「一緒に、寝る?」
「ふざけるな」
「なんで?」
「(俺の理性がもたない)」
「ダメ?」
「ダメに決まってるだろ」
「ケチ」
「(お前は俺を殺す気か?)」
そう言うとガシガシと乱暴に髪を拭きながら「もう電気消すぞ」とリモコンのボタンを押した皐月くん。