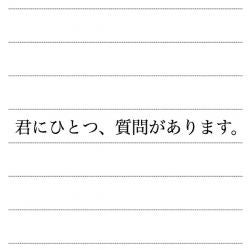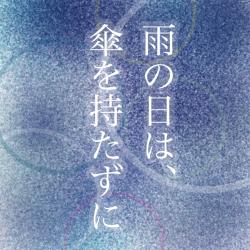気がつけば、私の唇は皐月くんの唇に塞がれていた。角度を変えて何度も何度も重なった唇はなんだかとっても甘くて。
でも、こんなところ見られでもしたらそれこそ私のスマホは鳴り止まなくなってしまう……。
「さ、つき、くん……」
ぎゅっと、皐月くんの胸を力のこもらない手で弱々しくも押し返せば、我に返った皐月くんはゆっくりと唇を離す。
「お前、帰ったら覚えてろよ」
「え……」
「とりあえず、今後ふらふらよそ見なんかすんな。他の男に隙を作るな。俺のだって自覚をもっと持て」
「……」
「返事は?」
「……はい」
「分かってんのか?」
「分かってるよ、てか、私はもうすでに皐月くんしか見えてないよ」
私が答えれば満足そうに笑った皐月くん。
「とりあえず帰ったら俺がいままで我慢してきた分、一気に返済してやる」
するりと再び指先を絡め取られスタスタと車の方へ歩いて行く皐月くんに引かれながら後を追う。
「え、あの、それはどういう……」
「……」
「……ねぇ、皐月くん、聞いてる?ねぇ!」
「あぁもう、うるさいな」
「え、痛ッーー、」
突然足を止めた皐月くんの背中に顔面を強打した私。いきなりなんなんだ、まったく。
皐月くんを見上げれば、綺麗な顔が迫ってきて、ヤバイまたこんなところでキスされると思い、どうしていいか分からず目一杯に瞼を閉じる。
するりと耳たぶを撫ぜられ、どきどきが加速した。
ちょんっと触れるだけのキスを落とされ、恐る恐る目を開ければ蠱惑的に微笑んだ皐月くんは、極上の甘い声音で私の全てを支配した。
「……さつ、き、くん?」
「バカ、そんなの俺の気がすむまでーーー、」