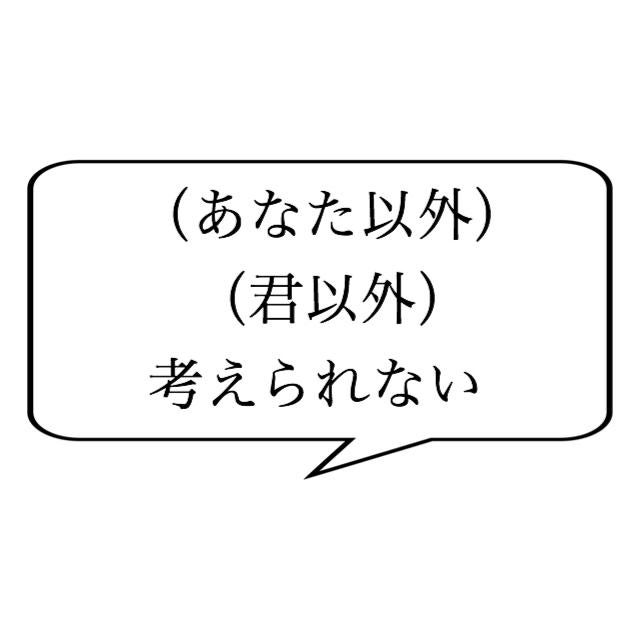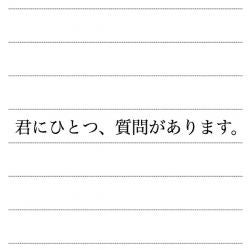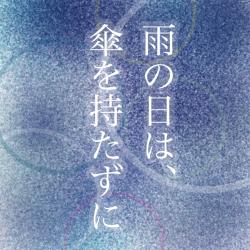半分だけ体温に包まれた体がなんだか寂しくて思わず皐月くんのコートをぎゅっと握った。すると「ん?」と優しい双眸がこちらに向く。
不意打ちのそれは、私の心臓を撃ち抜くには充分過ぎる凶器だった。どきどきが加速して、好きがまた増えていく。
「本当にごめん気づくの遅くなって、ごめん」
「……?」
皐月くんはそう言うと私のコートのポケットを指差す。ポケットに入っているのはスマホだ。誘導されるままポケットに手を入れスマホを取り出した。

届いていたメッセージを見て「パスタが食べたい!」とリクエストをすれば皐月くんは眉尻を下げて優しく笑った。
「(あのね、皐月くん。バカだと言われても、なにがあっても、私は、)」
「(君が例えどうしても俺が嫌で、俺以外を選んだとしても、俺は、)」