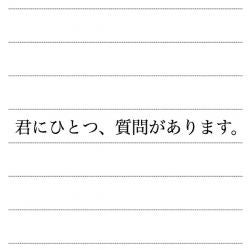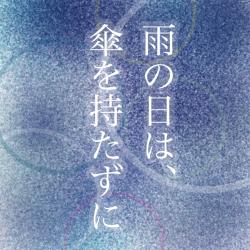「じゃ、俺こっちだから」
「……うん、あの、」
「俺的にいままで通り友達でいてくれたら嬉しいんだけど」
「もちろん、そんなのこちらこそ」
「あと、俺のこと好きになったときはすぐ教えて!」
「ごめん、それは無理かもです……」
「……」
「あのね私、いま好きな人のこと本当大好きで、その人がいなくなるって思うのさえ嫌で、」
「うわ、最後にめちゃめちゃ突き刺さるお言葉ありがとうございます」
「あ、いやあの、ごめんなさい……」
「いやいや、冗談。本気にするなよ」
優しく笑った杉野くんが、どことなく泣き出しそうに見えてしまった。
「……うん」
「じゃ、また、明日」
一方的にそう言うと私の住むマンションとは逆の方に向かって歩いていった杉野くん。きっと気まずくならないようにしてくれているのだろうと彼の優しさに胸がキューッと熱くなる。
「……ありがと」
「なにが?」
「……え、」
ぽつりと独白を溢し杉野くんの背中を見つめていれば、背後から聞こえてきた、低めの甘い声音。
その声の主は他でもない。くるりと振り返れば、黒のコートに身を包んだ皐月くんがコンビニの袋を持って立っていた。