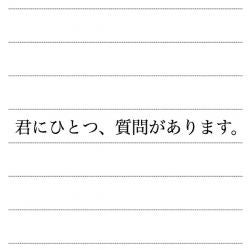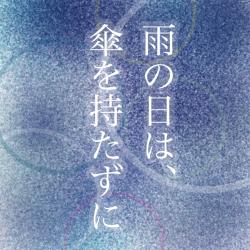「なあ、さっきのなに?」
「いや、なに?もなにも、なんにもないというか……」
「胡桃は本当に嘘が下手な」
「……人として上手なよりは下手なほうがいいかと」
「うるさい」
「……はい、すみません」
キョロキョロ視線を彷徨わせた私に、皐月くんの言葉が突き刺さった。本日2度目だ。“嘘をつくのが下手”だと言われたのは。
射抜くような視線に耐えきれず、縋るように自分の紺色のロングコートのポケットをぎゅっと握りしめた。
私の家の扉の前で、私を挟み壁に手を付く皐月くん。これは所謂、女子の憧れ壁ドンというやつで間違いない。
間違いないのだけれど、不機嫌なその表情は少女漫画で女子をきゅんきゅんさせるそれとはまるで違う。どちらかといえば敵を追い詰めた時のような、犯人逮捕的なそんな感じだ。
壁ドンとはもっとこうトキメキのあるものであってほしいと、切に願った。
それに、11月のこの時間はもう寒いので早く家に入りませんか?という本音を言いたいのも正直なところで。
「嘘なんかついてないというか……」
「視線キョロキョロし過ぎ、嘘、下手過ぎ」
至近距離で見つめた皐月くんのお顔は、あいも変わらず整っていて、眉間に皺なんか寄せていたら、かっこいい顔が台無しじゃないかなんて、私を睨む彼のお顔の心配をしていれば、
「なに、違うこと考えてんの?」
「……え、」
どうやら、目の前のイケメンには私の思考が筒抜けらしい。
ちなみに、この言葉を言われたのも本日2度目だ。私はどうやら相当分かりやすい生き物らしい。