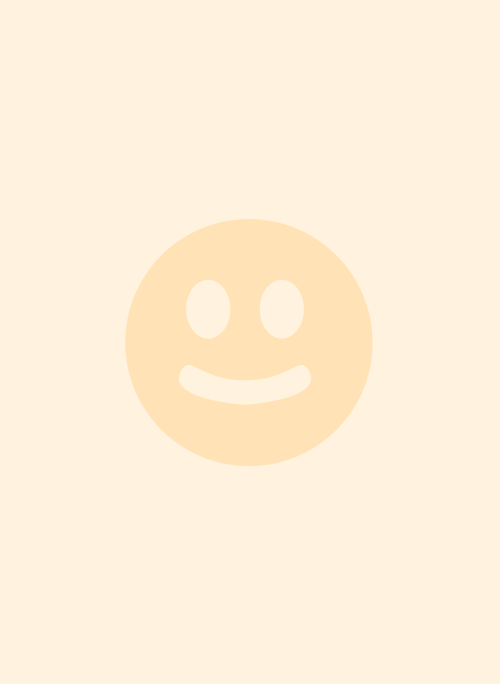「たすく……、お前、そんなやつだったかよ……」
天井を向いた俺の後頭部に諦めをにおわせた弱々しい声が落ちてきた。
「人の為に頭下げるタマじゃねえだろ」
貴史ちゃんの口調は、もはや教師のものではなかった。
俺は頭をあげる。
「うん。俺もびっくりい。
でも、俺、自信あるね。キョン以外の為には絶対、頭下げないって」
「……わかったよ。響ちゃんの気持ちも、たすくの気持ちも。」
そう言って、貴史ちゃんはため息混じりに苦い笑顔を浮かべた。
愛犬がお気に入りの靴をかじってしまったときに「しょうがないなあ」と言うような。
「貴史ちゃん、大好き」
「前にも同じセリフ聞いたよ。それで俺は随分、下位なんだろ」
「あ、ばれた?」
貴史ちゃんは、しっしっ、と手の甲で空気中の塵を掃くような仕草を見せた。
「響ちゃんを追っかけろよ、たすくが。
俺の――」
「ストーップ」
俺は、顔の前で腕をクロスさせて×印を作った。貴史ちゃんの言葉を遮る。
「俺の、の後は言わないの。
じゃ、俺、行くわ。
俺が行ったら、貴史ちゃん、泣いてもいいから、ね」
俺は、貴史ちゃんに背を向けて歩みを進めた。
貴史ちゃん『俺の代わりに』って言おうとしやがったぜ。
後ろの方で「泣くか、アホ」と呟く声が聞こえた。そして扉が閉まる音が後を追う。
あのね、俺は、貴史ちゃんの代わりじゃないの。
代わりに追い掛けるんじゃないんだから。
そこんところは、譲れないねえ。絶対。
天井を向いた俺の後頭部に諦めをにおわせた弱々しい声が落ちてきた。
「人の為に頭下げるタマじゃねえだろ」
貴史ちゃんの口調は、もはや教師のものではなかった。
俺は頭をあげる。
「うん。俺もびっくりい。
でも、俺、自信あるね。キョン以外の為には絶対、頭下げないって」
「……わかったよ。響ちゃんの気持ちも、たすくの気持ちも。」
そう言って、貴史ちゃんはため息混じりに苦い笑顔を浮かべた。
愛犬がお気に入りの靴をかじってしまったときに「しょうがないなあ」と言うような。
「貴史ちゃん、大好き」
「前にも同じセリフ聞いたよ。それで俺は随分、下位なんだろ」
「あ、ばれた?」
貴史ちゃんは、しっしっ、と手の甲で空気中の塵を掃くような仕草を見せた。
「響ちゃんを追っかけろよ、たすくが。
俺の――」
「ストーップ」
俺は、顔の前で腕をクロスさせて×印を作った。貴史ちゃんの言葉を遮る。
「俺の、の後は言わないの。
じゃ、俺、行くわ。
俺が行ったら、貴史ちゃん、泣いてもいいから、ね」
俺は、貴史ちゃんに背を向けて歩みを進めた。
貴史ちゃん『俺の代わりに』って言おうとしやがったぜ。
後ろの方で「泣くか、アホ」と呟く声が聞こえた。そして扉が閉まる音が後を追う。
あのね、俺は、貴史ちゃんの代わりじゃないの。
代わりに追い掛けるんじゃないんだから。
そこんところは、譲れないねえ。絶対。