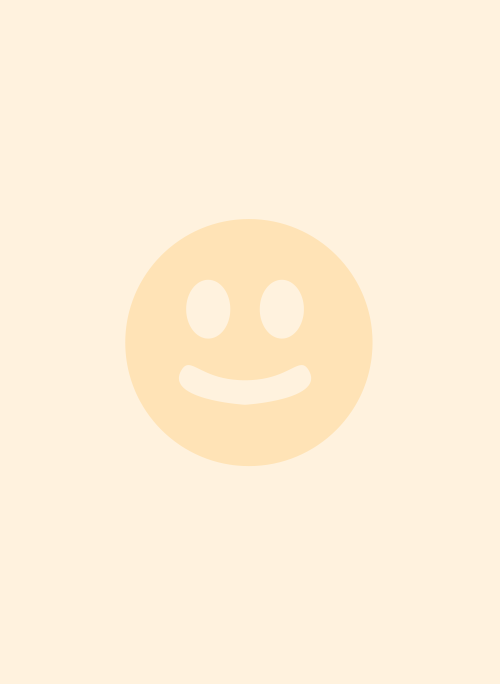「コットン、怒るとかわいい顔がだいなしよ?」
「うっさいわね、あんたは、どうしてすぐ――」
持ち前のヒステリーを発揮するコットンの唇に、俺は人差し指を重ねて耳元で囁いた。
「うるせーよ。言いたくねぇっつってんだよ。俺を怒らせるな、琴美」
俺のささやきに固まるコットン。
「たすく……わたしはただ……」
「あー、もう。彼女のしつけは彼氏の役目でしょ、ヒデ。
ヒデがしつけしないなら、俺がおとなしーい女に調教しちゃうよー」
「たすく、悪かった。でもよ、琴美は、たすくが心配なんだよ」
ヒデは、コットンを背中に隠して、申し訳なさそうに頭をかく。
「わかってるよ。コットンは、昔っから心配症だからねぇ。
でも、嫌なもんは嫌。言いたくないの。じゃ、また明日」
ヒデとコットンに背中を向けた。
「たすくのバカヤロー!」
コットンの叫びが背中で砕ける。
俺は、純情商店街の奥に向かって歩みを進めた。
皮膚の水分を容赦なく奪う冷たい風は、胸のモヤモヤも一緒に奪ってくれないだろうか。