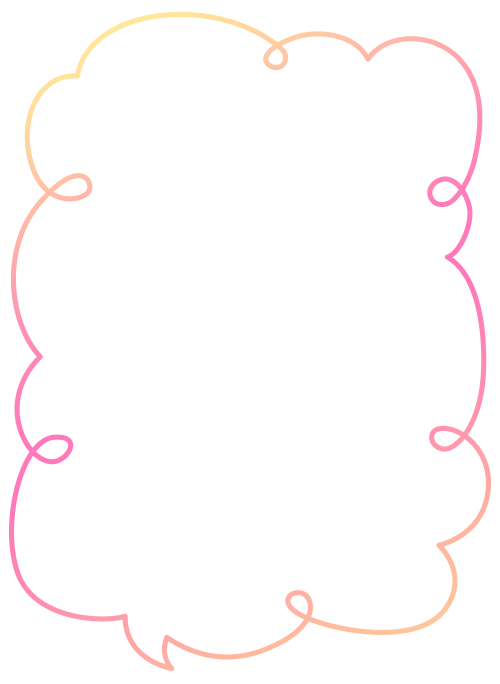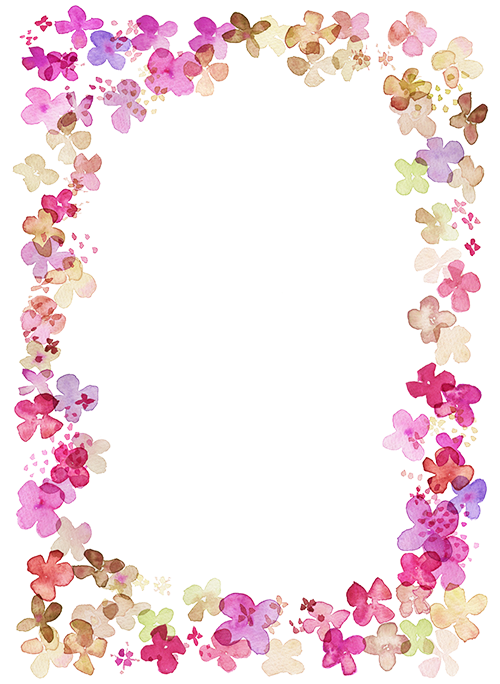あたしはベッドの下にある上履きに足を入れ、勢いよく立ち上がった。
カーテンを勢いよく開くと、後輩二人と目が合った。
二人は目を見開き、何か恐ろしいものでも見たかのように慌てて立ち上がって後ずさりした。
「……どいて」
「あ、彩乃先輩……あのっ……」
「どけって言ってんの!!」
行く手を塞ぐようにして立ち尽くす後輩に苛立ちながらその体を突き飛ばすようにどかそうとしたとき、吐き気は限界に達した。
「うっ、う!!」
両手で口元を押さえても指の間から溢れ出てくる吐しゃ物がポタポタと床にシミを作る。
「えっ、なに……嘘でしょ……」
「うわっ、マジで……」
後輩たちの冷めた声が耳に届く。
もうどうでもよかった。
もうどうなったってよかった。
もう、あたしなんてどうなったっていい。
必死に抑えていた手を口元から離すと、あたしは込み上げてくる吐き気にあらがうことなく、そのまま床にすべてを吐き出した。
「ヤバっ、あたしも気持ち悪くなってきた……!」
「とりあえず、ここでよっ!!!」
後輩はあたしを心配する様子もなく慌てて保健室を飛び出していく。
あたしにもしも人望があれば、こういう時後輩は助けてくれたんだろうか。
「大丈夫ですか?」という優しい声の一言でもかけてくれたんだろうか。
手についた吐しゃ物を保健室の水道で洗い流して口をゆすぐ。
制服が一切汚れなかったのが不幸中の幸いだ。
そうだ。そうだった……。
あたしは部内の誰かがミスすればそれを鬼の首を取ったように責め上げはしたものの、誰かが最高のプレーをしても褒めることはなかった。
どこかケガをしたと聞いてもねぎらいの言葉一つ欠けず、「ちゃんと準備体操したわけ?気が抜けすぎてるんじゃない?」と嫌味を吐いた。
すべてはあたしの日頃の行いが招いたせい。
今、ようやくそれに気付かされた。
目の前の鏡には真っ青な顔の自分が映っていた。
「あたし、こんな顔だったっけ……?」
鏡に映る自分はバレーをしているときの凛とした理想の姿ではなく、目の吊るしあがった嫌な醜い女の顔をしていた。
カーテンを勢いよく開くと、後輩二人と目が合った。
二人は目を見開き、何か恐ろしいものでも見たかのように慌てて立ち上がって後ずさりした。
「……どいて」
「あ、彩乃先輩……あのっ……」
「どけって言ってんの!!」
行く手を塞ぐようにして立ち尽くす後輩に苛立ちながらその体を突き飛ばすようにどかそうとしたとき、吐き気は限界に達した。
「うっ、う!!」
両手で口元を押さえても指の間から溢れ出てくる吐しゃ物がポタポタと床にシミを作る。
「えっ、なに……嘘でしょ……」
「うわっ、マジで……」
後輩たちの冷めた声が耳に届く。
もうどうでもよかった。
もうどうなったってよかった。
もう、あたしなんてどうなったっていい。
必死に抑えていた手を口元から離すと、あたしは込み上げてくる吐き気にあらがうことなく、そのまま床にすべてを吐き出した。
「ヤバっ、あたしも気持ち悪くなってきた……!」
「とりあえず、ここでよっ!!!」
後輩はあたしを心配する様子もなく慌てて保健室を飛び出していく。
あたしにもしも人望があれば、こういう時後輩は助けてくれたんだろうか。
「大丈夫ですか?」という優しい声の一言でもかけてくれたんだろうか。
手についた吐しゃ物を保健室の水道で洗い流して口をゆすぐ。
制服が一切汚れなかったのが不幸中の幸いだ。
そうだ。そうだった……。
あたしは部内の誰かがミスすればそれを鬼の首を取ったように責め上げはしたものの、誰かが最高のプレーをしても褒めることはなかった。
どこかケガをしたと聞いてもねぎらいの言葉一つ欠けず、「ちゃんと準備体操したわけ?気が抜けすぎてるんじゃない?」と嫌味を吐いた。
すべてはあたしの日頃の行いが招いたせい。
今、ようやくそれに気付かされた。
目の前の鏡には真っ青な顔の自分が映っていた。
「あたし、こんな顔だったっけ……?」
鏡に映る自分はバレーをしているときの凛とした理想の姿ではなく、目の吊るしあがった嫌な醜い女の顔をしていた。