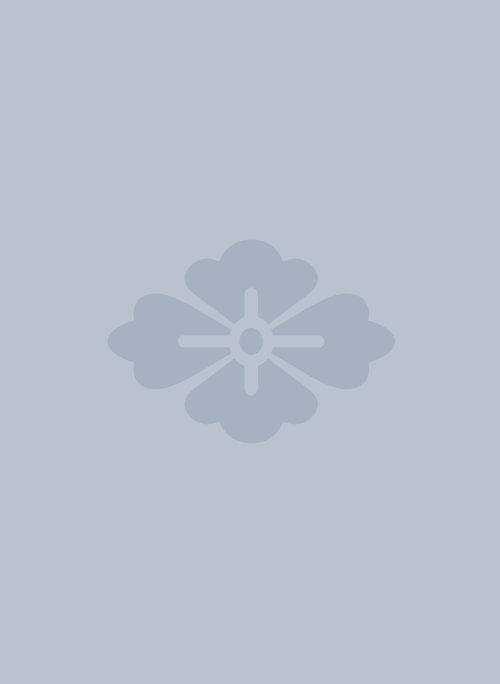時計の音が嫌いだった。
楽しい時間はあっという間に過ぎていく。
「お嬢様、そろそろお戻りになりましょう」
透き通るような白い手が、真っ白いシロツメクサをばらまいた。
今日は一日中不機嫌な顔をしている。
鏡を見なくとも、それは幼いながら自覚できていた。
「楽しい時間も、終わってしまうことが分かっているとつまらないのね」
深くため息をつきながら立ち上がる。
また、退屈なお城へ戻るのだと思うと憂鬱で仕方がない。
本当はまだ遊んでいたい。
お城じゃないどこか遠くへ連れ出して欲しい。
わがままはいくらでも言えるけど、それを言ったところで世界は変わらないことを知っていた。