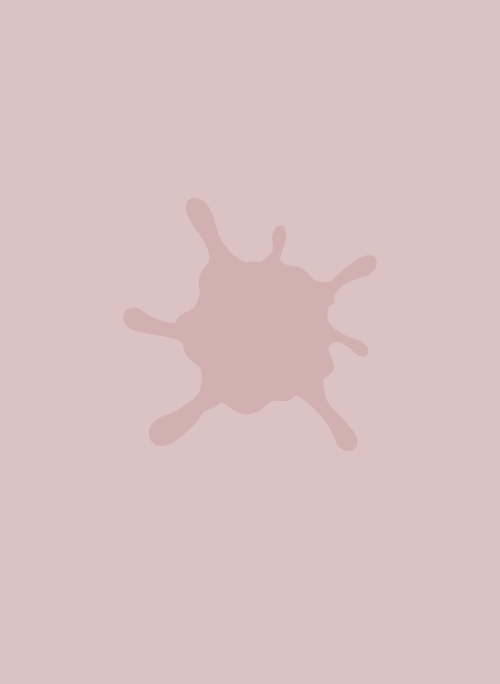面白くないと何度感じただろう。友達と彼氏は違うと頭で分かっていても、いつかきっと来るであろうその日に独占欲が沸かずに居られない。
私が一番では無くなるんじゃないかと。
そんな事思っても仕方ないし、自分でも一番が何なのか分かってないわけだけど。自分勝手にもほどがあるだろう。
せめてもと、嘘笑いを浮かべて経緯を見守るつもりだった。
「ちぃの事、よろしく。後一押しだから頑張れ」
「かっかかか神楽!?」
「じゃっ、僕、祈ちゃんと帰んから、ちぃまた後で」
「は?」
見守るつもりだっただけに、突如の事に、私?と疑問を浮かべたのも束の間、「行こう」と促されて断れる筈もなく、赤面して今にも叫びそうになっていた千代を横目に教室から廊下へと足を運んだ。
「……――」
急だな、と感じた。急に会話を切り上げて帰ろうとしたように私には見えた。
チラリと隣を歩く神楽君を見れば陽気に鼻歌なんて歌っているので、別段何かがあったわけでもなさそうだ。
そもそも、この短時間であの明るさに何かがあるだなんて考えつきもしない。
出来る事と言えば足を動かし、下校するだけ。