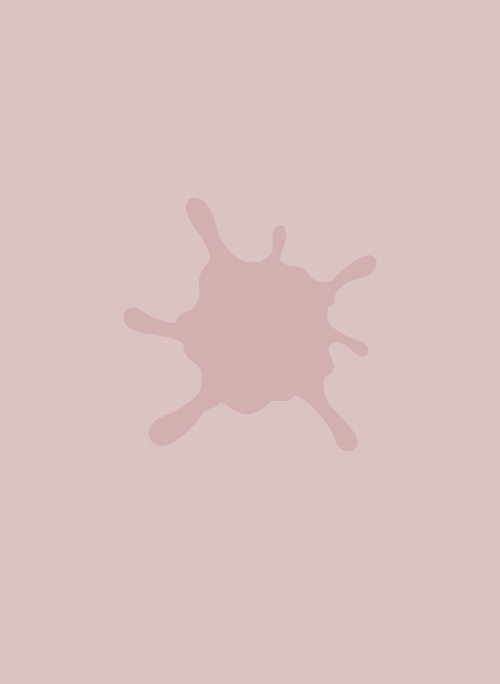彼を少々見上げる形で見ていると、瞳は右へ左へ、上へ下へ、何かを探すかのように微妙に揺らいだ。だが、直ぐに私の視線に焦点が合わせられる。
それでも何か、目の奥を探られている感覚がした。いいや、確かに彼は探ったのだ。私を。
「アンタの話聞いてるとさ、俺の事知りたいって言うより自分の事知ってほしいって感じする」
「……――」
それは個人的な分析。それでも、的確だろう。間違っていないのだ。彼を知りたい以上に私は私を知って欲しい。
と言われて気がついたのだが。
「ヤらせてくれたお礼に、聞いてあげる。一個だけね」
唖然とする私を他所に彼は私が手に持ちっぱなしになっていたスカーフに手を伸ばし、ご丁寧にキッチリ直してくれる。
スルリとスカーフから離れていく白い手を見つめた。
「……」
鋭い。なんて物じゃ片付かない。見透かされている。
何だか悔しくなる反面嬉しかった。私の事見てくれてると。自惚れかもしれないが。
「――じゃ、私が透佳さんと出会った日に起こった出来事」
だから、吐き出したいままに。吐き出せるままに。この蟠りを。
「私……私の誕生日なのに、お母さんが男の人連れ込んで、性行為してたんです。……親のソレ程気持ち悪い事ってないと思いません?」
スッと体温が下がる感覚。笑おうとしたのに引きつった。
まだ私はあの日の事を鮮明に覚えている。私自身でそれを上書きしようとしても、無理な話なのかもしれない。
私の吐露に彼は率直過ぎる言葉で返してきた。
「――……それで処女捨てるアンタも大概気持ち悪いけど」