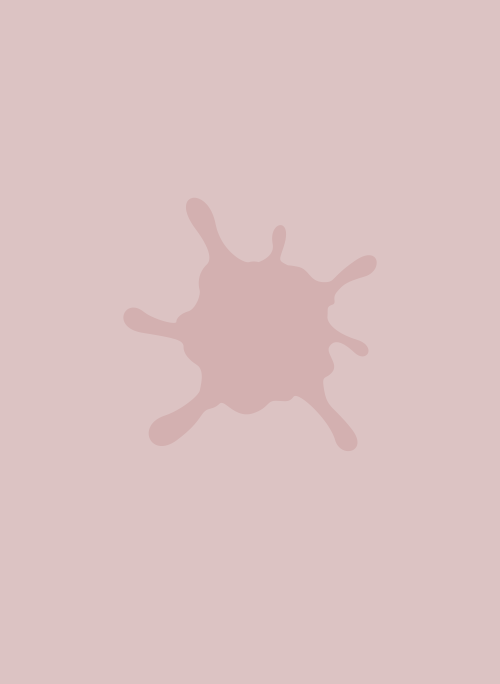「――……」
廊下まで休み時間は騒がしい。人の間をすり抜けて足を進める。
嘘、吐いた。わざとそうしたのだが、何も通知していないディスプレイが更に嘘を吐いた事実を突き付けて私を抉る。大嫌いで吐きたくもない嘘を吐いた自分に嫌悪した。
普段から“私”を取り繕って嘘で塗り固めているのに、それは見ない振りをしているくせに、明確な嘘を吐けば気持ち悪さが競り上がってくる。
何とも厄介で、心底自分が面倒くさく感じた。
電話なんて来ていなければ掛ける気もない。やる事がない。
フラフラと校内を歩き回る。とりあえずは、静かな場所を目指した。
これは確かに独占欲なんだろう。同時に、何に置いても私を一番にしてほしいと言う自分勝手な我が儘。好きな人よりも他の友達よりも。
だって、私を見てほしい。
只の友達にさえ、こう思ってしまう私はおかしいのだろうか。
でも、誰も私をちゃんと見てくれなかった。一番になんかしてくれなかった。嘘吐きばかりなのだ。
「!」
気持ちが更に沈みそうになったその時、不意に手の内から振動が伝わった。タイミングが良すぎた。
すがる気持ちで画面を見やる。
「……」
独りよがりはお互い様。彼を選んだ最大の理由は興味を持ったからだが、別の理由は色の無い瞳に私だけが映れると確信したからだ。
例え一瞬でも。
「もしもし?」
少し間を開け、聴こえたのは淡々とした声。
『……ねぇ、今日すごくアンタとヤりたいから家に来てよ』
直球な言葉を何にも包まず投げてくる彼。私はその一瞬でも、私が映れば満足なのだ。