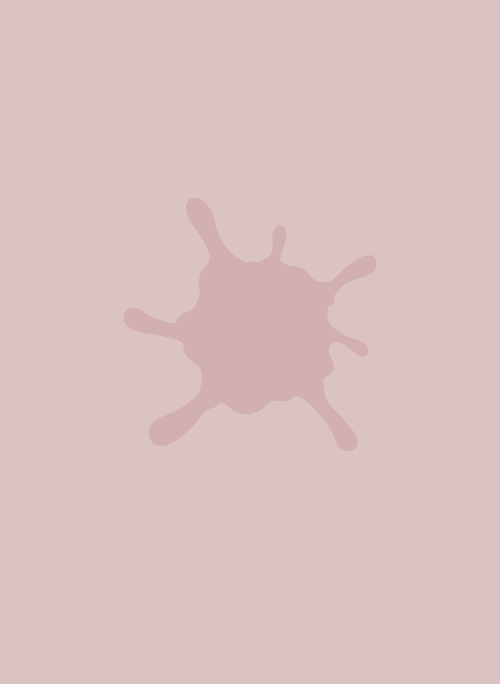殺す。などと言う物騒な言葉を携えて、何を言っているのだ彼は。
「な、何……」
「俺は成人していて、アンタは間違いなく未成年。泣いてみせれば社会的に弱いのはどっちか、馬鹿でも分かるでしょ?」
それは、先に神楽君にも同じような事を言われている。
神楽君程はっきりとは言わないけれど、透佳さんは私に復讐紛いに行動しろと言うのだ。彼はそうやって私に武器を持たせる。
いいや、そんな危うさはずっと彼に付きまとっていた筈だ。それでも私と今まで一緒に居てくれた。
それは優しさなんかじゃなくて利害が一致していただけにすぎない。
けれど今、食い違いが発生すれば守るべき秘密など何処にもないのだ。
拒絶する彼と、引き下がる私。もしかすると、その図が煩わしいのかもしれない。そう言ってしまってまで、きっぱりと切ってしまいたいのだろう。
これが最後の手段。彼が受け入れる一つの私の行動。縋る事も怒る事も快楽も何も要らないのだ。
引き止める術なんてどこにも持たせようとしない。
だけど。
「そんなこと……」
「俺はアンタにだったら殺されてもいいよ。好きにしたらいい」
あくまでも私に答えを委ね、自分ではどうもしない。彼は悪くて狡い大人だ。
それが大人なのだ。
でも私は。いつだって私が殺してしまいたかったのは自分自身で。こんな臆病な私で、こんな醜い私で。
とっくに要らなかったのは“いい子で可愛い私”
「っ!!」
なら、こんな私を終わりにしてしまえばいいのだ。
テーブルに無造作に置かれていたカッターの刃を限界まで押し出して、中学生の頃から伸ばし始めた髪に当てた。