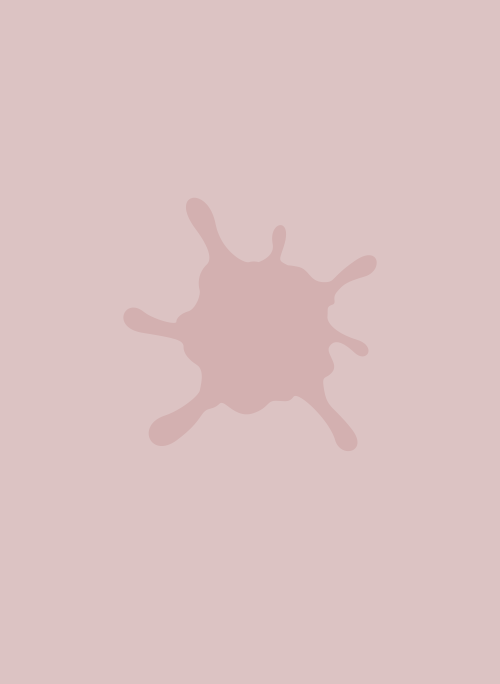「アンタって、お嬢様気質だよね。わがままで自分勝手。自分だけ見てくれなきゃ嫌なくせして、周りの人間の事に気づこうともしない。都合のいい人がいたら、そっちばっかり見て」
そうだよ。そうだった。
「ね、自分で気づいてる?アンタはずっと俺が好きって言ってたけど、俺の事なんか好きじゃないって事」
ああ、でもなんて酷い事を言うのだろう。
「自分を見てくれる人が好きで、自分が見られているその事実が好きだって言ってたようなもんだよ」
唇を噛み締める。
彼はただただ私を突き放したいのだ。距離を一定で保ちたいだなんて、そんな生易しいものではない。
本当にこんな私は要らないのだ。
「――……もう、そろそろ潮時だね」
彼は今度こそ静かに別れの言葉を告げた。
それはさながら死刑宣告のような重さを持っていた。