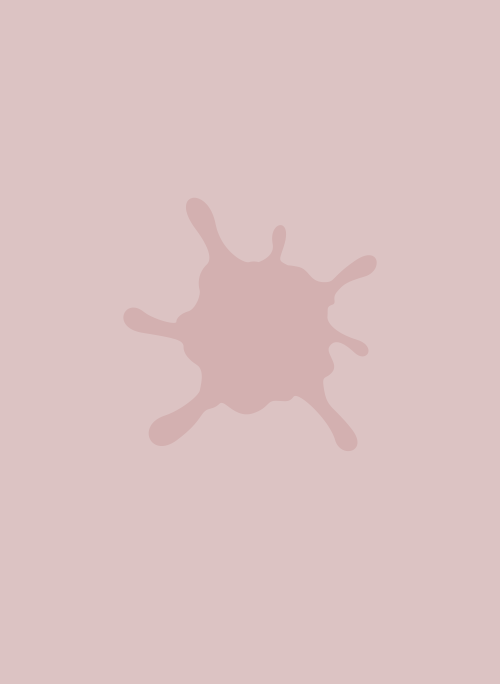ああ、頭が重い。
項垂れた頭は長い黒髪によって私の顔を隠してくれる。
「私、何も変わってない筈です。だってずっとこんなに満たされない。貴方が居なければ一人ぼっちでこの想いを抱えて……そんなのは嫌。嫌なんです」
でも、私は先の彼の言葉に怒りを持ってしまった。それは答えだったのではないか。
「……何も分かってないね。さっきの話に何の意味があると思ってるの?」
「さっき?どの話の事ですか?ううん、貴方の話はいつだって意味なんてなかった筈です」
「俺にとってはね。でもアンタにとっては全部意味があったはずだよ。自覚したんでしょ?」
彼はよく、脈絡もなにもない話をしていた。人の心理のような信憑性もなにもなさそうな話。
でも、確かに私は全部を受け流す事などで来ていなかった。
私は、他人の視線に言葉に敏感だった。
「刷り込み。俺に対して最初にしたんだとして。再刷り込みを神楽君にしてるんだよ。ね、そうでしょ?」
ガクンと力が入らなくなった。脱力にも似た感覚は、急激な倦怠感を連れてきた。
私は彼の言葉を享受するだけだった。