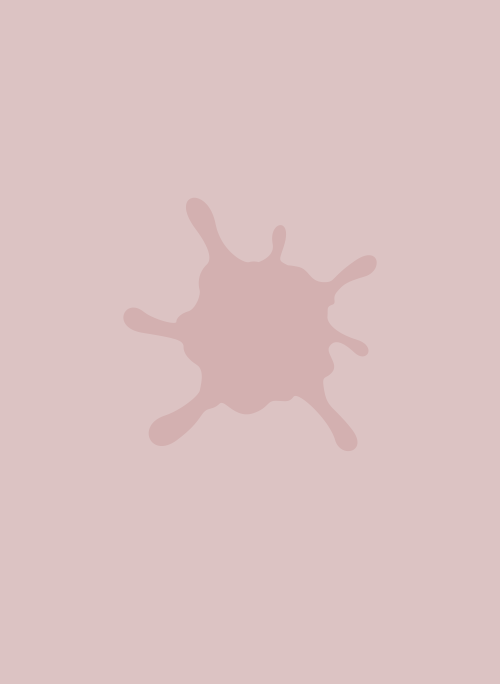「目が覚めたか?」
教壇の向かい側に座る生徒に向け、声を掛けた。
最後の生き残りである、片平洋子に。
「片平には謝らないといけない。最後の1人を助けると言ったが、先生は考え直した。やっぱり、学校そのものを根本から壊してしまわないといけないと思う」
スタンガンの名残か、まだ完全に意識を取り戻していない、唯一の生徒に向かって語りかける。
「今のこの、教育現場が間違っている。生徒に甘く、教師に厳しいだけの現場は、教師を志す熱い気持ちを刈り取ってしまうんだ。抗(あらが)えば抗うほど、身動きが取れなくなってしまう」
僕は目を閉じた。
かつて「先生」と呼ばれることを夢見た時期を、懸命に思い返そうと___無理だ。胸に込み上げてくるものはなにもない。
ただの燃えかすが、焦げつく匂いがするだけ。
「だから学校を、教室を跡形もなく消す必要がある。片平にだけ背負わせるような辛い思いはさせない。ここで先生と一緒に__消えよう」
「やめ、て」
「すまない」
そう言って僕は、マッチを1本すった。
2人の間で、小さな火が揺らめく。
「やめて、こんなの__」
まだ朦朧としているのだろう、片平は立ち上がろうとするが、足に力が入らないんだ。
もう、この教室はガソリンを撒いて取り囲んである。
「これにて、授業を終わる」
マッチを、放り投げた。