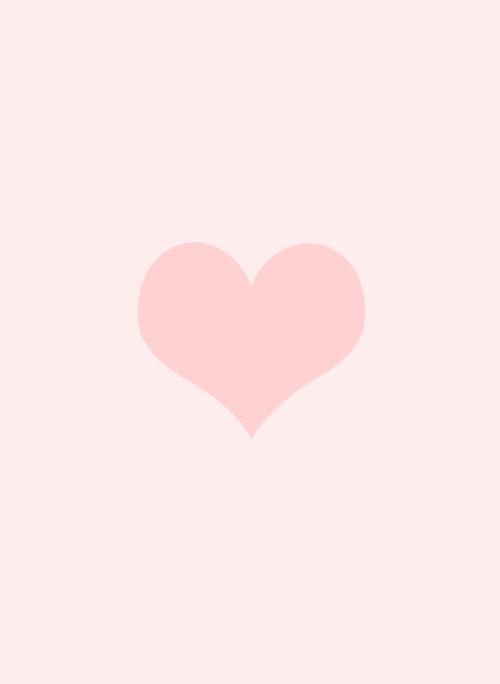「大袈裟ですよ。名将とは、友達だっただけですし」
「友達とは、言い得て妙じゃ。一国の皇子が、友達など……」
「一国の皇子という事実は明かしていましたよ。それでも、あちらの地域はよくしてくれました」
それは全ては、黎祥を守り育んでくれた人がいたから。
率先して、黎祥たちを守ろうとしてくれた人がいたからだ。
「雲飛(ウンヒ)殿は……殺されたのですよね。先帝に」
「ええ。……妾は止められませんでした」
黎祥を守ろうとして、殺された。
先帝を弑したのは、ある意味、私怨だったとも言える。
「ただ……殺されたのは、雲飛殿ではありませぬ」
「え?」
「殺されたのは、鳳雲様……」
「鳳雲?……それは、先々帝の同母弟では」
名前は聞いたことがある。
けれど、死刑されたもの達の名の中に、その名前はなかった。
黎祥が知っている限りであったのは、師の雲飛殿の名前だけ。
「もう、頃合かと思うての……」
「?」
「約束しておくりゃれ。黎祥」
「……?」
真っ直ぐな瞳に囚われ、首を傾げる。
騒がしい、兄弟達の声が聞こえなくなるような、そんな威圧感を彼女に感じる。
伊達に、後宮を何十年も守ってきたわけじゃないということか。
「李家から来る、新しき妃を愛すると」
「……」
「愛は、努力だけでどうにかなるものでは無い。さりとて、もとよりあるものを再燃させることは可能であろう」
「……」
そう言われて、ハッとした。
皇太后の言う、李家からの新しき妃というのは―……。