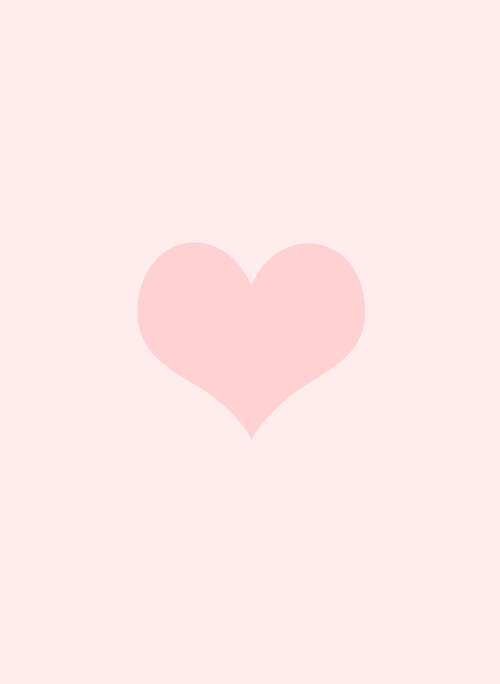(確か、あの時一番震えていたのも、鏡佳姉上だった)
全身、血塗れ。
もう、誰の血か分からぬほどに汚れた黎祥と見えた時、甲高い声で叫んだ鏡佳姉上は、その場で気を失ってしまった。
最も、それが正しい事だったのかもしれない。
第一皇女の麗宝姉上は喜びを隠せないって感じだったし、
第二皇女の姉の顔は殺した後に見たし、
第三皇女の彩姫姉上は深くお辞儀をしてきたし、
第五皇女の妹も気がつけば、物言わぬ骸と化していた。
第六皇女の灯蘭もまた深く感謝してきて、
第七皇女の露珠はただ、母親の手を強く握ってた。
そう考えれば、灯蘭は勿論、彩姫姉上も中々に度胸の座っている方だと感じる。
「……確かに、祥星様の娘ですもの。やりかねないわ」
皇太后が額を押さえて。
「それで……本日は、どのような用件でしょう?」
心配している楚太昭華に皇太后と話し合って決めたことを報告すると、
「あの子のために……皇恩、感謝致します」
と、深々、頭を下げてきた。
「近々、貴女にも会わせよう。娘を預けるのだから、話しておきたいだろう?」
「けれど、私は後宮の妃で……」
「私がいいって言ってダメなことは、この国にはない」
楚家は、皇家に従順である。
何でも、昔、父が楚家を救ったことがあるそうで。
見返りを求めず、ただ、皇家に仕えたいそうだ。
そう微笑みかけると、呆然とした楚太昭華。