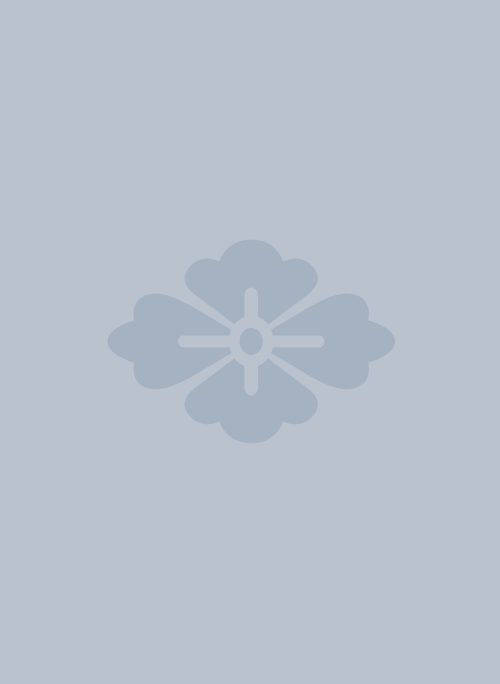(寒い……寒くて体が震えるのに、お腹と背中はとても熱い……)
燃えるような熱さと痛みに、ルルはただ耐えているしかない。
「ルルさん!」
呼ぶ声に答えるように、ルルはうっすらと目を開け、自分を見下ろしているノエンの顔を見た。
とても近い距離にいることから、自分は今、ノエンの腕の中にいるのだろう。
寒くて、痛くて、熱いというのに。ノエンに包まれていると分かると、胸の奥に優しい光が灯る。
ノエンがラッドを憎んでいたと知った時、ノエンのルルに対する言葉は嘘だったのだと気付いた。
「…………ノエン……さんは……私がラッドと……一緒……いたか……私に……優しか……の?」
息が苦しくて、上手く言葉を発せられない。
けれども、ノエンの耳にはしっかりと届いていた。
悲しげに眉を下げ、肩を震わせているノエンの姿は、まるで置いていかれた子供のようだ。
「私は……マンティコアに、ラッドの母親に……家族を奪われたんです」
ノエンは手短に、家族のこととここに来た目的を話した。
「私はラッドを殺すためだけに生きてきた。……そのために誰が死のうとも構わなかった。……なのに」
ルルだけは、殺したくなかった。
ルルを傷付けたくはなかった。
「……ノエンさ………私……ね」
「喋らないでください!血を止めなければ」
ルルの背中からは、止めどなく血が流れており、顔も青白くなっていく。
早くしなければと思いながら、もう手遅れなのだと気付いていた。
リュート達は何のつもりなのか、先程から黙って二人のやり取りを見守っている。
「…………私…………ね」
ルルは力を振り絞り、左手でノエンの頬へと手を伸ばす。
言うつもりは無かった。けれども、やはり言わずにはいられなかった。
「……ノエンさんが……好き……」
「……っ」
知っていたルルの想い。気付かないふりをしていた想いが、ルルの口から紡がれたことで、どしりと重く、深くのしかかった。
死にかけの少女の言葉と言うのは、こんなにも自分を掻き乱すものなのだろうか。
「貴方が……私を……どう思っ……としても……私は貴方が……」
ルルの瞼は重くなり、瞳の光は濁っていく。
伸ばした手はノエンの頬に赤い痕を残し、だらりと下がる。
涙で濡れた視界のせいで、ノエンの顔が良く見えない。
(……駄目……せめて、最後にもう一度)
最後にもう一度だけ、自分の想いを伝えたい。
「……好きっ―」
息を吐き出すのと同時に、ルルの意識は途絶えた。
ノエンは声の出し方を忘れたかのように、口を開きかけてはまた閉じた。
『……』
低い唸り声と、大きな影が二人を覆い隠す。
呆然と見上げると、ラッドが口を開けていた。
燃えるような熱さと痛みに、ルルはただ耐えているしかない。
「ルルさん!」
呼ぶ声に答えるように、ルルはうっすらと目を開け、自分を見下ろしているノエンの顔を見た。
とても近い距離にいることから、自分は今、ノエンの腕の中にいるのだろう。
寒くて、痛くて、熱いというのに。ノエンに包まれていると分かると、胸の奥に優しい光が灯る。
ノエンがラッドを憎んでいたと知った時、ノエンのルルに対する言葉は嘘だったのだと気付いた。
「…………ノエン……さんは……私がラッドと……一緒……いたか……私に……優しか……の?」
息が苦しくて、上手く言葉を発せられない。
けれども、ノエンの耳にはしっかりと届いていた。
悲しげに眉を下げ、肩を震わせているノエンの姿は、まるで置いていかれた子供のようだ。
「私は……マンティコアに、ラッドの母親に……家族を奪われたんです」
ノエンは手短に、家族のこととここに来た目的を話した。
「私はラッドを殺すためだけに生きてきた。……そのために誰が死のうとも構わなかった。……なのに」
ルルだけは、殺したくなかった。
ルルを傷付けたくはなかった。
「……ノエンさ………私……ね」
「喋らないでください!血を止めなければ」
ルルの背中からは、止めどなく血が流れており、顔も青白くなっていく。
早くしなければと思いながら、もう手遅れなのだと気付いていた。
リュート達は何のつもりなのか、先程から黙って二人のやり取りを見守っている。
「…………私…………ね」
ルルは力を振り絞り、左手でノエンの頬へと手を伸ばす。
言うつもりは無かった。けれども、やはり言わずにはいられなかった。
「……ノエンさんが……好き……」
「……っ」
知っていたルルの想い。気付かないふりをしていた想いが、ルルの口から紡がれたことで、どしりと重く、深くのしかかった。
死にかけの少女の言葉と言うのは、こんなにも自分を掻き乱すものなのだろうか。
「貴方が……私を……どう思っ……としても……私は貴方が……」
ルルの瞼は重くなり、瞳の光は濁っていく。
伸ばした手はノエンの頬に赤い痕を残し、だらりと下がる。
涙で濡れた視界のせいで、ノエンの顔が良く見えない。
(……駄目……せめて、最後にもう一度)
最後にもう一度だけ、自分の想いを伝えたい。
「……好きっ―」
息を吐き出すのと同時に、ルルの意識は途絶えた。
ノエンは声の出し方を忘れたかのように、口を開きかけてはまた閉じた。
『……』
低い唸り声と、大きな影が二人を覆い隠す。
呆然と見上げると、ラッドが口を開けていた。