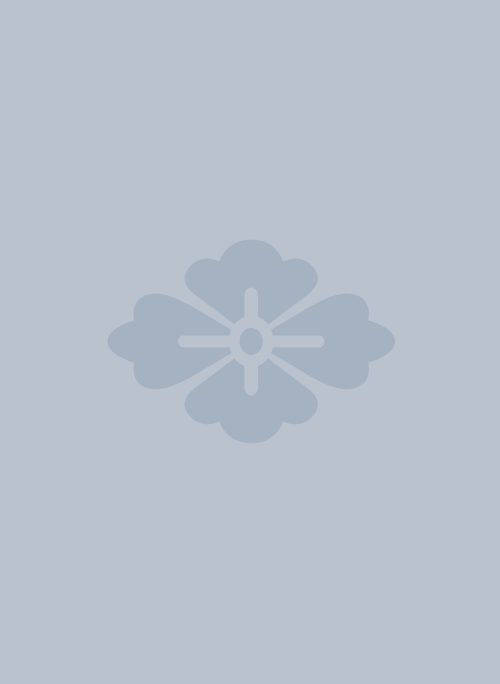重く引きずるような音が辺りに一瞬だけ響いた。
人々の視線の先には、地面に転がった斧。
「……はぁ……はぁ」
放り投げた体勢のまま、ルルは肩で息をしていた。
「何の真似だ?!ルル!!」
団長の怒鳴り声が、静かな会場に響き渡る。
「……」
ルルは姿勢を戻すと、俯いて肩を震わせていた。
「ふっ……ふふふ!」
「な、何がおかしい?」
含み笑いをするルルを、団長は気味の悪いものを見るような目で見ていた。
観客達もルルの様子を、息を飲んで見ている。
「あははは!………………出来るわけがない」
大きな声で笑ったかと思えば、ポツリと小さく呟く。
「?」
意味が分からないと、訝しげな視線を送る団長に、ルルはキッと睨み返した。
「出来るわけがないじゃない!私がラッドを面倒見てきたのは、ラッドを家族のように思っていたから。私が得られなかった家族の愛情を、せめてラッドには与えたかったからよ!」
自分が欲しかった親の愛。
父も母も、記憶の隅に掠れてしまいそうなほど小さい頃には、もしかしたら愛してくれた時があったかもしれない。
けれども、はっきりと覚えている記憶の中の自分は、いつも両親の愛情を求めて泣いていた。
二人に好かれる子供になろうと、「良い子」になろうと必死だった。
それでも、結局得ることは出来なかったが。
だからこそ、ルルは一欠片でも良いから、ラッドに与えたかった。
受け取るだけの愛もあるだろう。けれども、ルルは与える愛を選んだ。
血の繋がった家族でも、恋人でも、ましてや人間でもないこの幻獣に。
「……もし私がラッドを殺してしまったら、私は本当に『私』を失ってしまう」
片耳を失った時、自分はもう自分では無くなったような気がした。
けれども、それは間違いだ。
どんな姿をしていようとも、ルルの中身が変わるわけではないのだから。
大切にしてきたものを、自分の手で壊してしまったその時、ルルはルルで無くなってしまうと、ラッドを前にして初めて気付いた。
「ラッドを殺すくらいなら、いっそラッドに食べられて死ぬことを選ぶわ!」
持っていた鞭を床へと叩き付けると、鞭はバチバチと音をたてる。
すると、ラッドの首輪が外れた。
人々の視線の先には、地面に転がった斧。
「……はぁ……はぁ」
放り投げた体勢のまま、ルルは肩で息をしていた。
「何の真似だ?!ルル!!」
団長の怒鳴り声が、静かな会場に響き渡る。
「……」
ルルは姿勢を戻すと、俯いて肩を震わせていた。
「ふっ……ふふふ!」
「な、何がおかしい?」
含み笑いをするルルを、団長は気味の悪いものを見るような目で見ていた。
観客達もルルの様子を、息を飲んで見ている。
「あははは!………………出来るわけがない」
大きな声で笑ったかと思えば、ポツリと小さく呟く。
「?」
意味が分からないと、訝しげな視線を送る団長に、ルルはキッと睨み返した。
「出来るわけがないじゃない!私がラッドを面倒見てきたのは、ラッドを家族のように思っていたから。私が得られなかった家族の愛情を、せめてラッドには与えたかったからよ!」
自分が欲しかった親の愛。
父も母も、記憶の隅に掠れてしまいそうなほど小さい頃には、もしかしたら愛してくれた時があったかもしれない。
けれども、はっきりと覚えている記憶の中の自分は、いつも両親の愛情を求めて泣いていた。
二人に好かれる子供になろうと、「良い子」になろうと必死だった。
それでも、結局得ることは出来なかったが。
だからこそ、ルルは一欠片でも良いから、ラッドに与えたかった。
受け取るだけの愛もあるだろう。けれども、ルルは与える愛を選んだ。
血の繋がった家族でも、恋人でも、ましてや人間でもないこの幻獣に。
「……もし私がラッドを殺してしまったら、私は本当に『私』を失ってしまう」
片耳を失った時、自分はもう自分では無くなったような気がした。
けれども、それは間違いだ。
どんな姿をしていようとも、ルルの中身が変わるわけではないのだから。
大切にしてきたものを、自分の手で壊してしまったその時、ルルはルルで無くなってしまうと、ラッドを前にして初めて気付いた。
「ラッドを殺すくらいなら、いっそラッドに食べられて死ぬことを選ぶわ!」
持っていた鞭を床へと叩き付けると、鞭はバチバチと音をたてる。
すると、ラッドの首輪が外れた。