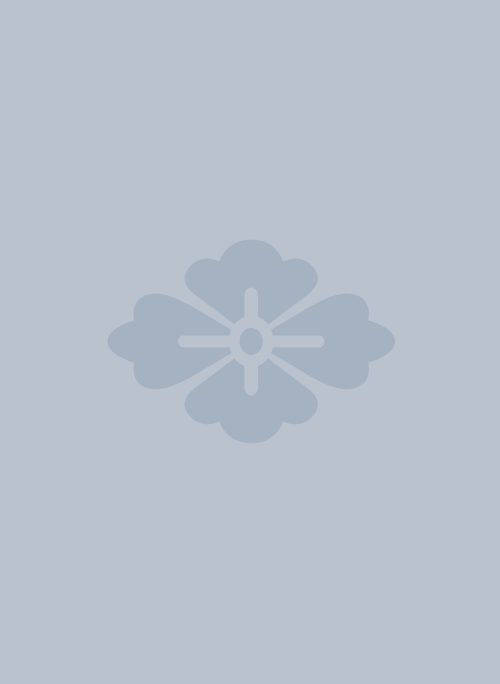そして、運命のショーの日。
「本日お集まりの皆様の中には、このサーカスで起きた忌まわしい出来事のことが耳に入ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう」
団長の話声が、どこか遠くで聞こえるような気がする。
「罪深き幻獣マンティコアの最後の姿を、ぜひご覧下さい!」
(……団長さんは、こんな時でも楽しそうね……)
ニタッとした、ねっとり張り付くような笑みが、ルルは大嫌いだった。
だが、そんな顔も今日で見納めだ。
(……死ぬ時って、こんなに穏やかな気持ちになるものかしら?)
悲しみも怒りも、恐怖ですら、今は何も感じない。
(…………あぁ、でもまだ未練があるわ)
まだ彼にちゃんと伝えていない。
ルルは相変わらずの仏頂面を晒している青年へと近寄る。
「リュート」
「何の用だ?もやし」
相変わらず過ぎて、何故か笑えてくる。が、ルルは何時ものように頬を膨らましてリュートを睨んだ。
「失礼ね!……ねぇ、リュート」
「……」
「私ね、貴方のこと、そんなに嫌いじゃなかったわ。意地悪だったけど、優しい時もあったもの」
目を伏せ、ルルはリュートから貰った耳当てへと手を添えると、息を吐き出す。
そして、短く息を吸い込むと、リュートの目を真っ直ぐ見た。
「だから……だからね。私、貴方が居てくれて良かったと思ってるの。この耳当てを渡してくれた時にちゃんと言えなくてごめんなさい。…………ありがとう」
リュートが居てくれて良かった。リュートの不器用な優しさに救われていたと、その思いを込めた「ありがとう」の言葉。
「……!」
その気持ちは、リュートに届いただろうか?
けれども、届いていなくても良いと思えた。見返りなどいらない。
ルルは、ルルの言いたいことを言っただけなのだから。
「では、長らくお待たせいたしました!『ラッドの処刑ショー』の始まりです!」
「……行くわね」
最後は、せめて笑っていよう。
彼の心の中に、不格好でも情けない顔は残したくない。
大切な友人であり、兄であり、弟だった彼の思い出に残る顔は、笑顔が良い。
「ルル!」
「!……さようなら」
初めて呼ばれた名前。それを嬉しく思いながら、ルルは返事を返さず、舞台へと上がった。
「本日お集まりの皆様の中には、このサーカスで起きた忌まわしい出来事のことが耳に入ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう」
団長の話声が、どこか遠くで聞こえるような気がする。
「罪深き幻獣マンティコアの最後の姿を、ぜひご覧下さい!」
(……団長さんは、こんな時でも楽しそうね……)
ニタッとした、ねっとり張り付くような笑みが、ルルは大嫌いだった。
だが、そんな顔も今日で見納めだ。
(……死ぬ時って、こんなに穏やかな気持ちになるものかしら?)
悲しみも怒りも、恐怖ですら、今は何も感じない。
(…………あぁ、でもまだ未練があるわ)
まだ彼にちゃんと伝えていない。
ルルは相変わらずの仏頂面を晒している青年へと近寄る。
「リュート」
「何の用だ?もやし」
相変わらず過ぎて、何故か笑えてくる。が、ルルは何時ものように頬を膨らましてリュートを睨んだ。
「失礼ね!……ねぇ、リュート」
「……」
「私ね、貴方のこと、そんなに嫌いじゃなかったわ。意地悪だったけど、優しい時もあったもの」
目を伏せ、ルルはリュートから貰った耳当てへと手を添えると、息を吐き出す。
そして、短く息を吸い込むと、リュートの目を真っ直ぐ見た。
「だから……だからね。私、貴方が居てくれて良かったと思ってるの。この耳当てを渡してくれた時にちゃんと言えなくてごめんなさい。…………ありがとう」
リュートが居てくれて良かった。リュートの不器用な優しさに救われていたと、その思いを込めた「ありがとう」の言葉。
「……!」
その気持ちは、リュートに届いただろうか?
けれども、届いていなくても良いと思えた。見返りなどいらない。
ルルは、ルルの言いたいことを言っただけなのだから。
「では、長らくお待たせいたしました!『ラッドの処刑ショー』の始まりです!」
「……行くわね」
最後は、せめて笑っていよう。
彼の心の中に、不格好でも情けない顔は残したくない。
大切な友人であり、兄であり、弟だった彼の思い出に残る顔は、笑顔が良い。
「ルル!」
「!……さようなら」
初めて呼ばれた名前。それを嬉しく思いながら、ルルは返事を返さず、舞台へと上がった。