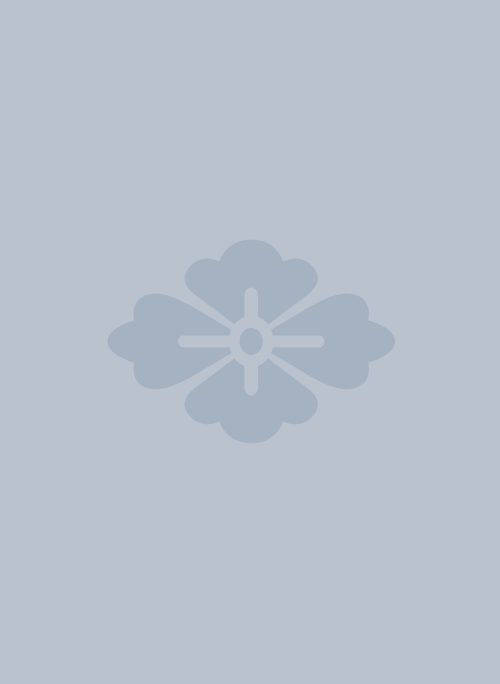『……』
「……っ」
涎を垂らしながら、ラッドはルルを見ている。
今のラッドの目には、自分は餌にしか見えていないのだろう。
それが、余計に恐怖を駆り立てた。
アコーディオンを演奏する気にもなれず、ルルはラッドの檻の前で立ち尽くす。
食いちぎられた右耳が疼いて、花飾りへと手を伸ばした。
(……あなたと私は、同じなんかじゃない)
これは、自分の自惚れと甘さが招いたことなのだ。
「……座りなさい」
『……グルルル』
「大人しくしなさい」
少し言葉を強くするが、それでもラッドは唸ることを止めない。
ルルは渡されていたスイッチの付いた鞭をラッドの前に差し出した。
「……この鞭に付いてる赤いボタンが見える?……これはね、あなたの首輪の起動ボタンなの。こうやって押すのよ」
出っ張った赤いボタンを押すと、カチッと音がした。
瞬間、ラッドは目を見開き、顔を床へと押し付ける。
「……首輪にはね、魔力を封じる役割と、幻獣に応じて、別々の苦痛を与えるの。ラッドのは強力な電撃を与えるわ。身体中が痺れて、動けないでしょう?」
淡々と、ルルは冷めた声で語った。
ボタンをもう一度押すと、楽になったのか、ラッドは顔をあげる。
「……私が檻の扉を開けるまで、大人しく座りなさい」
ラッドはこちらを睨み付けたまま、大人しく座った。
ギラギラとした目から、ラッドの怒りや憎しみが伝わる。
ルルは檻の鍵を外して扉を開けると、横へとずれた。
「……出なさい」
『……』
牙をまた剥き出すと、ルルもまた赤いボタンをラッドに見せた。
「……言うことを聞きなさい。出るのよ」
『……』
唸るのを止め、ラッドは檻の外へと出る。
(私は……とうとう一番やりたくなったことをやってしまった。……もう、前のようにラッドと接することは出来ない)
これからは、命令でラッドを動かし、縛り付けるのだ。
処刑されるのはショーの最中。ルルとラッドが一緒にいられるのも、後わずか。
もう、あの温かい体温を全身で感じることは出来ない。
噛み殺される恐ろしさと、目の前で吹き飛んだ男の姿が、脳裏に焼き付いて離れない。
死ぬのは怖い。爆弾で吹き飛ばされるのも、人魚のように首を落とされるのも怖い。
でも、仕方の無いことだと諦めた。
「……」
部屋を出ていくラッドの後ろ姿を見ながら、ルルは唇を噛み締める。
その瞳から流れているものに気付かないふりをして、ラッドを追って部屋を出た。
「……っ」
涎を垂らしながら、ラッドはルルを見ている。
今のラッドの目には、自分は餌にしか見えていないのだろう。
それが、余計に恐怖を駆り立てた。
アコーディオンを演奏する気にもなれず、ルルはラッドの檻の前で立ち尽くす。
食いちぎられた右耳が疼いて、花飾りへと手を伸ばした。
(……あなたと私は、同じなんかじゃない)
これは、自分の自惚れと甘さが招いたことなのだ。
「……座りなさい」
『……グルルル』
「大人しくしなさい」
少し言葉を強くするが、それでもラッドは唸ることを止めない。
ルルは渡されていたスイッチの付いた鞭をラッドの前に差し出した。
「……この鞭に付いてる赤いボタンが見える?……これはね、あなたの首輪の起動ボタンなの。こうやって押すのよ」
出っ張った赤いボタンを押すと、カチッと音がした。
瞬間、ラッドは目を見開き、顔を床へと押し付ける。
「……首輪にはね、魔力を封じる役割と、幻獣に応じて、別々の苦痛を与えるの。ラッドのは強力な電撃を与えるわ。身体中が痺れて、動けないでしょう?」
淡々と、ルルは冷めた声で語った。
ボタンをもう一度押すと、楽になったのか、ラッドは顔をあげる。
「……私が檻の扉を開けるまで、大人しく座りなさい」
ラッドはこちらを睨み付けたまま、大人しく座った。
ギラギラとした目から、ラッドの怒りや憎しみが伝わる。
ルルは檻の鍵を外して扉を開けると、横へとずれた。
「……出なさい」
『……』
牙をまた剥き出すと、ルルもまた赤いボタンをラッドに見せた。
「……言うことを聞きなさい。出るのよ」
『……』
唸るのを止め、ラッドは檻の外へと出る。
(私は……とうとう一番やりたくなったことをやってしまった。……もう、前のようにラッドと接することは出来ない)
これからは、命令でラッドを動かし、縛り付けるのだ。
処刑されるのはショーの最中。ルルとラッドが一緒にいられるのも、後わずか。
もう、あの温かい体温を全身で感じることは出来ない。
噛み殺される恐ろしさと、目の前で吹き飛んだ男の姿が、脳裏に焼き付いて離れない。
死ぬのは怖い。爆弾で吹き飛ばされるのも、人魚のように首を落とされるのも怖い。
でも、仕方の無いことだと諦めた。
「……」
部屋を出ていくラッドの後ろ姿を見ながら、ルルは唇を噛み締める。
その瞳から流れているものに気付かないふりをして、ラッドを追って部屋を出た。