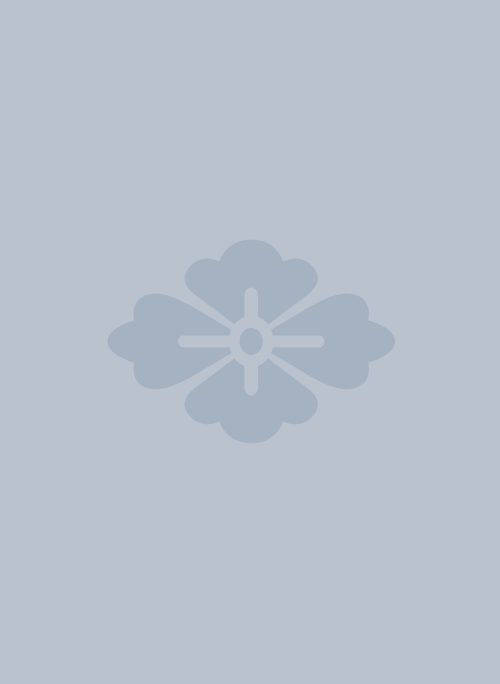ようやく痛みも引き、落ち着いた頃。ルルは団長に呼び出され、仕事部屋に来た。
ノックをしようとしては、手が震えてまた下へと下ろす。
そんなことを何度も繰り返していたが、逃げ道など無いのだと自分を叱咤し、ようやくノックをした。
「入れ」
うじうじと悩んでる間に、相当待たされていたのだろう。
苛立った団長の声がくぐもって聞こえ、ルルは覚悟を決めてドアを開けた。
「……何だ、それは?」
「……あ……これは……」
ノエンの前で情けない姿を晒してしまったと落ち込んでいたルルの元に、先日リュートがやって来た。
―いつまで世話を放棄する気だ?お前の分まで働かされる俺の身にもなれ。……は?こんな顔で部屋から出たくない?安心しろ、お前の顔は元から「こんな顔」だ―
リュートの言い草にイラつき、その後感情的になって、随分色々言った気がする。
何を言ったのかは覚えてないが、もしかしたら酷いことも言ってしまったかもしれない。
半ば八つ当たりのように何かを喚いていた。
そしたら、リュートは溜め息を吐いてから、背中にやっていた左手を前に差し出した。
リュートが差し出してきたのは、布で出来た花が付いた、片耳専用の耳当てだった。
ピンク色の何枚も重なった大輪の花は、とても可愛らしく、ルルはピタッと言葉を止めてそれを見ていた。
―妖精達が持ってきた花を参考に作ったやつだ。本物の花じゃ枯れるからな。これでもつければ?無い耳を見せるよりマシだろ―
押し付けられるように渡された耳当てを、ルルは暫く眺めていた。
そして、恐る恐る頭へと着ける。カチューシャは左耳の上までしか長さがなく、本当に右だけ塞ぐように作られていた。
「……やっぱり、マシになったな」
思った通りだと呟いたリュートの顔に、胸の奥が締め付けらた。
「自分で作りました。……商品としての見映えは、少しは良い方が良いかと思いまして」
リュートからと言いそうになったが、絶対に自分の名前は出すなと約束させられていた。
だから、咄嗟に自分で作ったと嘘を付いた。
嘘をつくのは、心が痛くなるから、あまり好きではないが。
「ほー。まだ商品として役立とうという気持ちはあったか。感心だな……ならば、ワタシが言うことも分かるだろう?」
「……」
「次のショーは、お前とラッドの処刑ショーだ。人生最後の演義だからな、後悔の無いようにやれよ?」
「……………はい」
ノックをしようとしては、手が震えてまた下へと下ろす。
そんなことを何度も繰り返していたが、逃げ道など無いのだと自分を叱咤し、ようやくノックをした。
「入れ」
うじうじと悩んでる間に、相当待たされていたのだろう。
苛立った団長の声がくぐもって聞こえ、ルルは覚悟を決めてドアを開けた。
「……何だ、それは?」
「……あ……これは……」
ノエンの前で情けない姿を晒してしまったと落ち込んでいたルルの元に、先日リュートがやって来た。
―いつまで世話を放棄する気だ?お前の分まで働かされる俺の身にもなれ。……は?こんな顔で部屋から出たくない?安心しろ、お前の顔は元から「こんな顔」だ―
リュートの言い草にイラつき、その後感情的になって、随分色々言った気がする。
何を言ったのかは覚えてないが、もしかしたら酷いことも言ってしまったかもしれない。
半ば八つ当たりのように何かを喚いていた。
そしたら、リュートは溜め息を吐いてから、背中にやっていた左手を前に差し出した。
リュートが差し出してきたのは、布で出来た花が付いた、片耳専用の耳当てだった。
ピンク色の何枚も重なった大輪の花は、とても可愛らしく、ルルはピタッと言葉を止めてそれを見ていた。
―妖精達が持ってきた花を参考に作ったやつだ。本物の花じゃ枯れるからな。これでもつければ?無い耳を見せるよりマシだろ―
押し付けられるように渡された耳当てを、ルルは暫く眺めていた。
そして、恐る恐る頭へと着ける。カチューシャは左耳の上までしか長さがなく、本当に右だけ塞ぐように作られていた。
「……やっぱり、マシになったな」
思った通りだと呟いたリュートの顔に、胸の奥が締め付けらた。
「自分で作りました。……商品としての見映えは、少しは良い方が良いかと思いまして」
リュートからと言いそうになったが、絶対に自分の名前は出すなと約束させられていた。
だから、咄嗟に自分で作ったと嘘を付いた。
嘘をつくのは、心が痛くなるから、あまり好きではないが。
「ほー。まだ商品として役立とうという気持ちはあったか。感心だな……ならば、ワタシが言うことも分かるだろう?」
「……」
「次のショーは、お前とラッドの処刑ショーだ。人生最後の演義だからな、後悔の無いようにやれよ?」
「……………はい」