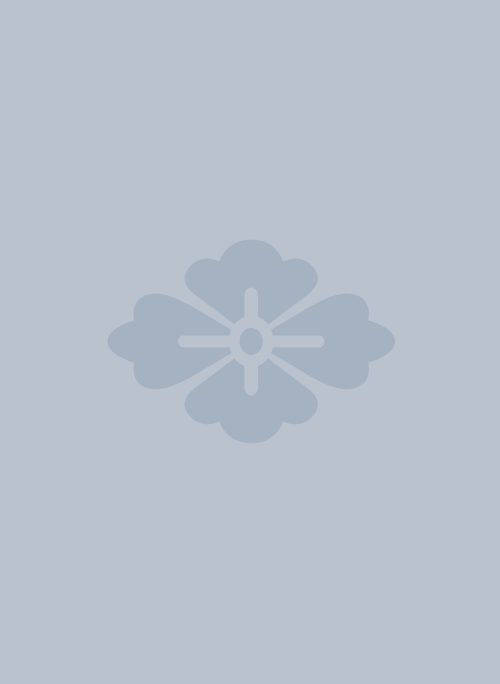そして、ショー当日。
柱の影から会場を覗くと、金持ちの人間が沢山ひしめき合っていた。
ショーが始まるまで、ガヤガヤと談笑している。
ルルとラッドの出番は後半なので、他の幻獣達の演義が終わるまで待機していろと言われた。
ファンファーレの音が鳴り響くと、ビクッとルルの肩が跳ねる。
分かっていても、どうも心臓に悪い。ただでさえ緊張していて、心臓が飛び出そうなほど脈打っているのに。
側にいるラッドは、大人しく座っているが、ファンファーレの音でキョロキョロと辺りを見回している。
ルルは落ち着かせるようにラッドの背を撫で、足元に用意しておいたアコーディオンを見つめる。
指示を出すだけでなく、演奏者として自分も注目されるのかと思うと、足が震えそうだ。
だからと言って、出来ませんなど言えない。
ファンファーレが止むと、団長が舞台の上で両腕を広げている。
実に簡潔に挨拶を済ませると、指を鳴らした。
すると、人魚が引き出され、歌を歌う。
とても美しい歌声だが、胸の奥が締め付けられるような、悲しい気持ちになる。
人魚の言葉は、自分達とはまた違う。だから、歌の歌詞の意味は分からない。
だが、悲しみを表したような歌だということは分かった。
だが、暫く歌い続けていた人魚は、血を吐き出した。
「!」
喉を手で押さえながら、人魚はそれでも歌を止めない。
(どうしよう。あの子死んじゃう)
人魚はついにぐったりと前のめりになる。水槽のガラスを伝う赤い雫が、ポタポタと地面を彩る。
そんな人魚のことを、観客は笑いながら見ていた。
ルルは歪んだ笑みを浮かべている人々に、足が震える。
「どうやら、人魚の寿命がきたようですね」
団長はニッコリと笑いながら、また指を鳴らした。
すると、今度は斧を持ったエルフがやってきて、人魚の隣に立つ。
「それでは、役目を終えた人魚に、皆さん盛大な拍手を送ってください。私の合図と共に、人魚の首が落ちます」
人々ははち切れんばかりに拍手を送り始めた。
(……止めて)
「三……二……一……」
高く掲げられた手が振り下ろされる瞬間、ルルは走り出した。
だが―。
「……あ……」
容赦なく団長の手は下へと下ろされ、エルフの斧も人魚の首へと落とされた。
飛び散った血、最後にちらりと見えた瞳に浮かんでいた涙。
観客達の歓声が、どこか遠くに聞こえる。
「……い……や……」
ドクドクと心臓が身体中を叩くように鳴り響き、全身から嫌な汗が流れ落ちる。
次に、胸の奥から吐き気が沸き上がり、ルルは叫びたくなって口を開けた。
だが、ルルの声は口から漏れなかった。
「……叫ぶな」
いつの間にか背後にいたエルフの少年に、ルルは口を塞がれていた。
「お前もああなりたくないのなら、叫ぶな。……耐えろ。生きていたいのならな」
「……」
涙が頬を伝う。
痛い、気持ち悪い。そういう感情と共に、死への恐怖が膨れ上がる。
「あいつに同情してる暇があったら、ラッドと自分のことを考えろ。これからも、こう言うことはいくらでもある。だから、その度にそんな様では生き残れない」
言い終わると、少年はルルの口から手を離した。
「……」
息の仕方が分からなくなったように、ルルはパクパクと口を閉じたり開けたりしていた。
(……私も、使えなくなったら……死ぬの?)
あんな風に笑い者にされながら、首を落とされるのかと思うと、怖くて仕方ない。
(やだ……死にたくない、死にたくない!)
死への恐怖から、ルルは立ち上がって舞台を見た。
人魚の死骸はもう片付けられ、妖精達がショーをしている。
その光景を、ルルはどこか虚ろな目で見ていた。
柱の影から会場を覗くと、金持ちの人間が沢山ひしめき合っていた。
ショーが始まるまで、ガヤガヤと談笑している。
ルルとラッドの出番は後半なので、他の幻獣達の演義が終わるまで待機していろと言われた。
ファンファーレの音が鳴り響くと、ビクッとルルの肩が跳ねる。
分かっていても、どうも心臓に悪い。ただでさえ緊張していて、心臓が飛び出そうなほど脈打っているのに。
側にいるラッドは、大人しく座っているが、ファンファーレの音でキョロキョロと辺りを見回している。
ルルは落ち着かせるようにラッドの背を撫で、足元に用意しておいたアコーディオンを見つめる。
指示を出すだけでなく、演奏者として自分も注目されるのかと思うと、足が震えそうだ。
だからと言って、出来ませんなど言えない。
ファンファーレが止むと、団長が舞台の上で両腕を広げている。
実に簡潔に挨拶を済ませると、指を鳴らした。
すると、人魚が引き出され、歌を歌う。
とても美しい歌声だが、胸の奥が締め付けられるような、悲しい気持ちになる。
人魚の言葉は、自分達とはまた違う。だから、歌の歌詞の意味は分からない。
だが、悲しみを表したような歌だということは分かった。
だが、暫く歌い続けていた人魚は、血を吐き出した。
「!」
喉を手で押さえながら、人魚はそれでも歌を止めない。
(どうしよう。あの子死んじゃう)
人魚はついにぐったりと前のめりになる。水槽のガラスを伝う赤い雫が、ポタポタと地面を彩る。
そんな人魚のことを、観客は笑いながら見ていた。
ルルは歪んだ笑みを浮かべている人々に、足が震える。
「どうやら、人魚の寿命がきたようですね」
団長はニッコリと笑いながら、また指を鳴らした。
すると、今度は斧を持ったエルフがやってきて、人魚の隣に立つ。
「それでは、役目を終えた人魚に、皆さん盛大な拍手を送ってください。私の合図と共に、人魚の首が落ちます」
人々ははち切れんばかりに拍手を送り始めた。
(……止めて)
「三……二……一……」
高く掲げられた手が振り下ろされる瞬間、ルルは走り出した。
だが―。
「……あ……」
容赦なく団長の手は下へと下ろされ、エルフの斧も人魚の首へと落とされた。
飛び散った血、最後にちらりと見えた瞳に浮かんでいた涙。
観客達の歓声が、どこか遠くに聞こえる。
「……い……や……」
ドクドクと心臓が身体中を叩くように鳴り響き、全身から嫌な汗が流れ落ちる。
次に、胸の奥から吐き気が沸き上がり、ルルは叫びたくなって口を開けた。
だが、ルルの声は口から漏れなかった。
「……叫ぶな」
いつの間にか背後にいたエルフの少年に、ルルは口を塞がれていた。
「お前もああなりたくないのなら、叫ぶな。……耐えろ。生きていたいのならな」
「……」
涙が頬を伝う。
痛い、気持ち悪い。そういう感情と共に、死への恐怖が膨れ上がる。
「あいつに同情してる暇があったら、ラッドと自分のことを考えろ。これからも、こう言うことはいくらでもある。だから、その度にそんな様では生き残れない」
言い終わると、少年はルルの口から手を離した。
「……」
息の仕方が分からなくなったように、ルルはパクパクと口を閉じたり開けたりしていた。
(……私も、使えなくなったら……死ぬの?)
あんな風に笑い者にされながら、首を落とされるのかと思うと、怖くて仕方ない。
(やだ……死にたくない、死にたくない!)
死への恐怖から、ルルは立ち上がって舞台を見た。
人魚の死骸はもう片付けられ、妖精達がショーをしている。
その光景を、ルルはどこか虚ろな目で見ていた。